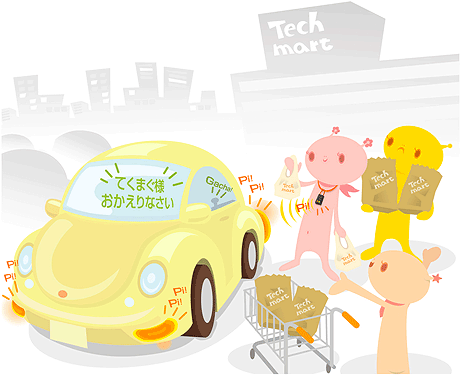テクのサロン
9. スティックひとつでクルマを操作 − バイ・ワイヤー技術の先進性 −

今、このページをご覧になっているみなさんの目の前には、パソコンとキーボードがあるはずですよね。そのキーボードのルーツが、欧文タイプライターであることもご存じでしょう。
どちらも、役割はほぼ同じ。「押し下げたキーに割り当てられている文字を、その先にある機構を介してタイプ紙やディスプレイに反映させる」ための装置ですが、構造はまったく異なります。タイプライターのキーは、その先につながっている「エスケープメント」と呼ばれる印字機構を物理的に動かすための「操作棒」としての役割を果たしています。対してパソコン用キーボードのキーは、内蔵する「キーボードマイコン」からパソコン本体へ、「今、このキーが押された」という信号を送信するためのスイッチです。
そう遠くない将来、スティックひとつでステアリング操作/アクセル操作/シフトチェンジまでをこなすバイ・ワイヤー技術が市販車で実現し、ドライバビリティの飛躍的な向上が見られるかもしれません。
物理的操作から電気的操作への変換
キーボードとは、もともと鍵盤楽器の鍵盤を指す言葉ですが、この分野でもタイプライターとパソコン用キーボードのような関係が見られます。ピアノの鍵盤は、背後にある本体の内部で「アクション」や「ダンパー」などの機構につながっていて、最終的に「ハンマー」が弦を叩くことで音を鳴らします。対して電子ピアノの鍵盤は、それぞれに割り当てられた電子音を発するためのゲートスイッチという役割になります。
このように、機械的・物理的な機構によって実現していた仕組みを、電気・電子的な仕組みに置き換える動きは、この四半世紀の間にさまざまな分野で一般化しています。ここでは、そのような動きを「バイ・ワイヤー(by Wire)化」と呼ぶことにします。
バイ・ワイヤーとは、もともとは航空機の世界で使われ始めた言葉です。機械的機構(メカニカル・リンク)が占めていた場所や経路を、信号線(ワイヤー)が置き換えることが語源です。
航空機の操縦系統は、操縦桿やペダルに対する操作の動きを、ケーブルやロッドなどの機械的機構を介してフラップやスロットルに伝えるメカニカル・リンクから始まりました。やがて操作力の負担を軽減することなどを目的に、要所を油圧で駆動する仕組みが取り入れられるようになります。
航空機の進化を、今も昔も主導している軍用機の場合、最も避けたいのは戦闘状態で被弾し、操縦不能におちいることです。そのためには、加速性能や旋回性能を高めるといったアクティブ(能動的)な手法によって「被弾しないようにする」ための設計要素と、万一被弾しても、エンジンや燃料タンク、操縦系等といった重要な部分になるべくダメージがおよばないようにするパッシブ(受動的)な設計要素の両方を、バランス良く取り入れることが重視されます。
パッシブな設計手法を突き詰めて行くと、「被弾させたくない機構が機体に占める割合を、可能な限り小さくしたい」という要求が出て来ます。そこで、「油圧機構は基本的にピストンとポンプで構成されているものであり、操作に対する作動量さえ適正に制御できれば、メカニカルな機構で駆動する必要はない」ことに気付いたエンジニア達がいました。彼らはロッドなどのメカニカルな機構を電気的な仕組みに置き換えることで、最も被弾させたくない主操縦系統が占める面積を減少させようと試み、モーターと油圧サーボによる新しい仕組みが考案されます。
このような機構が「フライ・バイ・ワイヤー」と呼ばれるようになり、70年代半ば以降は電子技術やコンピュータの進化とリンクして次々と実用化されてゆきます。民間機では、1988年にデビューしたエアバスA320が全面的にバイ・ワイヤー化された初めての機体です。民間機の場合、被弾云々を気にする必要はありませんが、スペース効率の向上、機体の軽量化、電子制御による自動航行システムとの親和性など、ある意味では軍用機以上の効能が実現できました。
最先端技術の実験場・F1で磨かれたアシスト機構
さて、自動車の世界でも、昨今バイ・ワイヤー化の動きが猛烈な勢いで進んでいます。その勢いは、おそらく今後20年程度の間で、自動車のカタチ自体を根本的に変えてしまうのではないか?と思わされるほどです。
はっきりとはわからないのですが、自動車の中で最初にバイ・ワイヤー化されたのは、おそらく方向指示器ではないかと思います。大昔の自動車の方向指示器は、レバーを操作することでロッドやケーブルやリンクが動き、通常は車体に格納されている長五角形などの指示板を外側に倒すことで曲がる方向を示していました。これが、自動車に使われる電装品が増えてゆく過程で、レバー自体はスイッチとなり、リレーなどで構成される電子回路を通じて方向指示灯(初期にはブレーキランプと兼用のものもありました)が点滅する構成に変わってゆきます。
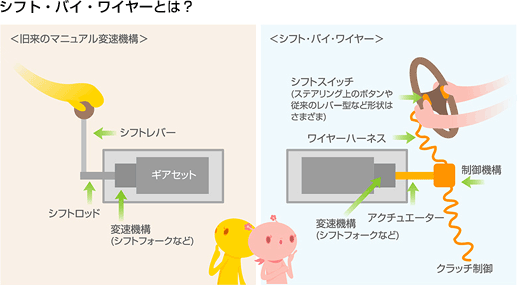
シフト・バイ・ワイヤーによって、変速操作は容易かつ確実なものになる。ドライバーの肉体的・精神的負担が軽減され、操作応答のタイムラグを減らす効果も実証されている。
昨今の電子制御技術の進化にともなうバイ・ワイヤー化のさきがけと言えるのが、1990年にフェラーリのF1マシンで採用された、「パドル・シフト」や「セミ・オートマティック・トランスミッション」と呼ばれる機構です。
それ以前はF1マシンといえども、市販の自動車が搭載するマニュアル・トランスミッションと基本的に同じ機構の変速機を使っていました。そのため、F1ドライバーでも操作ミスで順位を落としたり、エンジンを壊してしまったりすることがあったのです。また、サーキットによってはコーナリング中に変速しなければならないこともあります。当時のF1マシンにはステアリングのパワーアシスト機構など付いていませんでしたから、変速時には重い重いステアリングを片腕で保持しなければならず、特に体力や集中力が低下してくるレースの終盤では操作ミスの可能性が高まる、といった問題があったのです。
パドル・シフトは、そんな問題を解消するために考案されました。パドルとは「櫂(かい)」状のものを指す言葉です。コクピットの内部からシフトレバーが消え、代わりにステアリングホイールの裏側に、変速操作用の平たいレバー=パドルを備えます。パドルはその先にある変速機構のスイッチで、右側のパドルを押すとシフトアップ、左側のパドルがシフトダウンといったように役割が分けられています。
パドルを操作すると、以下のような手順で変速動作が行われます。
パドルを操作する
電子制御によってクラッチが切れる
電子制御によって強制的にスロットル開度を調整し、エンジン回転数を適正範囲に調整する
適正な回転数になったら、油圧を使った変速機構が変速操作を行う
変速が完了したらクラッチをつなげる
パドル・シフト=シフト・バイ・ワイヤーは、これだけの作業を瞬時に行なってしまうのです。変速操作に要する時間が短縮できる=クラッチを切っている時間が短縮できるので、駆動力を路面に伝えられる時間が増やせること、変速操作の確実性が高まることによるトラブルの低減、ステアリングホイールから手を離さずに変速操作ができることによるドライビングの自由度向上などなど、シフト・バイ・ワイヤーがもたらしたメリットはたいへん大きなものがあり、翌シーズンにはライバルチームもこぞって同様の仕組みを搭載してきました。さらに数年後には、サーキット形状などのデータやGPSと連動し、パドルの操作さえ不要とした「プログラムシフト/フルオートマ」へと進化します。
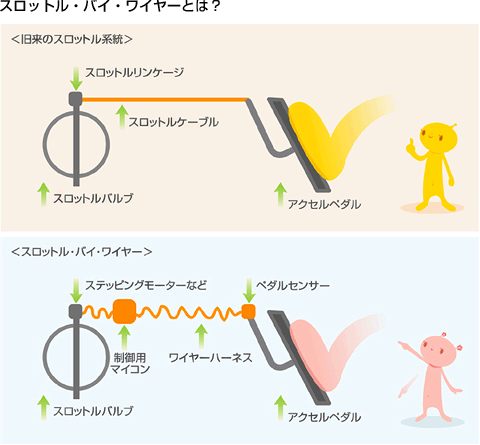
スロットル・バイ・ワイヤーのメリットは、操縦性安定性の向上もそのひとつに挙げられる。雨天時などの路面状況をタイヤのスリップで感じ取り、晴天時と違うスロットル開閉モードに自動調整することなどが可能となる。
パドル・シフトの次にF1マシンに用いられたバイ・ワイヤー機構は、アクセルペダルとスロットル制御の系統です。こちらは1990年代の初頭に採用例が登場しました。従来、ケーブルやリンケージなどの機構で接続されていたペダルとスロットルバルブの間を、バイ・ワイヤー化したのです。
こうすることで、まずスロットルケーブルやリンケージの破損といったトラブルを根絶できます。また、ペダルの踏み込み量とスロットルバルブ開度の関係を自在に設定し、しかもあらかじめ複数のモードを用意しておいて瞬時に切り替えることも可能になりますから、エンジンや路面のコンディションに応じて比率を調整したり、トラクション・コントロール機構と緻密に連携させる、といったことが可能になりました。
20年以上前から市販車にも採用済みの技術
話を市販車に移しましょう。実は、F1マシンにさきがけて完全な電子制御による「ロボット・シフト」機構を搭載した市販車がありました。1983年、いすゞASKAに搭載された「NAVI5」がそれです。NAVI5は従来通りのシフトレバーを使いますが、それ以外の仕組みは後にF1で採用されたものと基本的に同じです。それどころか、エンジンやブレーキなどとも連動する、当時としては画期的な統合電子制御システムでした。しかし時代が早すぎたのか、一部に熱狂的なファンを持ちつつも、登場から2年ほどでカタログから消えてしまった悲運のメカニズムです。
一般的にバイ・ワイヤー機構の認知が高まるのは、90年代の半ば頃です。ドイツのカスタムカー・ビルダーなどが、シフト・バイ・ワイヤー的な機構を採用し始めたことでクルマ好きの話題を呼びました。
ただし、当時のものはNAVI5やF1マシンのパドル・シフトほど複雑な機構ではなく、シフトレバーにセンサーを装着し、一定以上の力が加わると自動的にクラッチを切り、変速し終わるとクラッチをつなぐだけの比較的単純な機構でしたから、正しくは「クラッチ・バイ・ワイヤー」と呼ぶべきものかもしれません。しかし、クラッチ操作という、運転に習熟していない層にとってはかなり難易度の高い操作を不要とした効能は大きく、数年後にはルノーがコンパクトクラスの市販車に採用するなど、着実に採用例を増やしてゆきました。
さて、市販車のバイ・ワイヤー化によって得られるおもなメリットを、表にまとめてみました。90年代のバイ・ワイヤー化は、どちらかというと「F1マシンのテクノロジー」といったイメージ先行な存在だったのですが、昨今実現しつつあるバイ・ワイヤー化への流れは、クルマそのものの構造やカタチ自体を変えてしまう可能性を持つ、大きなムーブメントなのです。
たとえば、ステアリング・バイ・ワイヤー化によって、従来はシャフトとギアボックスが占めていたスペースが不要になりますから、そこに衝突安全のための機構を組み込んだり、室内スペースを拡大することができます。デザイン上の自由度も大きく高まるでしょう。ステアリングのパワーアシストの設定も完全にプログラマブルにできますから、その自由度は飛躍的に高まります。
軽量化できるメリットも実利の大きいものです。各種のシャフトやギアボックスは金属製の重いパーツですから、これがなくなるだけで車体の大幅な軽量化が実現でき、燃費や衝突安全性を高めることができます。他にも考えられる変更点は枚挙にいとまがないほどで、ある意味、銀塩カメラがデジタルカメラに移行した際と同じような「アーキテクチャー全体のリセット」が再現されるかもしれません。
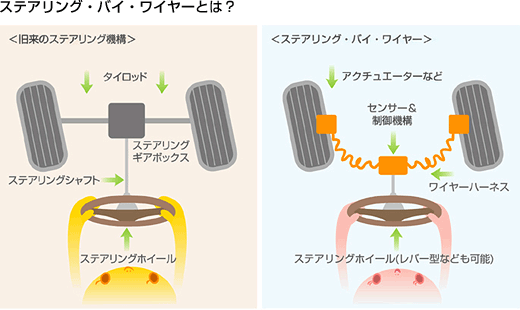
ステアリング・バイ・ワイヤーのメリットは、車体のフロントセクションの構造の自由度が飛躍的に高まること。操舵力、操舵量とフロントタイヤの動きの関係も、任意に、きめ細かく設定できる。
運転弱者の味方となるバイ・ワイヤー化
また、バイ・ワイヤー化は、身体に障碍を持つ方々へもたらす恩恵も大きいはずです。自動車はある意味で「モビルスーツ」としての側面も持っています。所有することで実現する「自由な移動」のメリットは、身体に障碍を持つ人にこそ大きいのです。しかし、障碍の内容によっては、通常の操作系を使って運転することが困難なこともままあります。
それをフォローするため、現在も後付けの運転補助装置が多々市販されています。それらの完成度も日々高まってはいますが、いかんせん「本来の操作系に付け加えるもの」としての限界があることは否定できません。また、コスト的にも補助装置の分、上乗せが必要になるわけです。しかし、たとえばステアリング・バイ・ワイヤー機能とスロットル・バイ・ワイヤー機能を併せ持つジョイスティック型の操作系が標準装備になれば、追加コストは不要になりますね。また、運転装置自体のデザイン自由度も大きく高まりますから、現状では運転が不可能なケースでもフォローできるような仕組みが実現できる可能性もあります。
このように、21世紀の自動車業界にとって、適材適所なバイ・ワイヤー化と、新しいデザインの模索は、最重要のテーマとなっているのです。
ちなみに、航空機の世界では昨今「フライ・バイ・ライト(Fly by light)」という言葉が使われ始めています。操作機構の動きと、機体全体の動きをセンサーでモニターしてコンピュータで統合的に処理し、フラップなどの動きを制御する機構ですが、センサーに光学系のものを使い、各セクションの間を接続する経路も光ファイバー・ケーブルを使うために「バイ・ライト」と呼ばれています。バイ・ワイヤーの進化版、光学版と言えるものですが、光信号を使うためノイズに強く、高速大容量のデータ通信が可能で、さらなる省スペース化と軽量化が実現できるといったメリットがあります。
ひょっとすると、バイ・ライト化に関しては、航空機よりも自動車が先行するかもしれません。すでに自動車には多くの光学センサーが搭載され、通信ケーブルの光ファイバー化も実用化されつつあるからです。
著者プロフィール:松田勇治(マツダユウジ)
1964年東京都出身。青山学院大学法学部卒業。在学中よりフリーランスライター/エディターとして活動。
卒業後、雑誌編集部勤務を経て独立。現在は日経WinPC誌、日経ベストPCデジタル誌などに執筆。
著書/共著書/監修書
「手にとるようにWindows用語がわかる本」「手にとるようにパソコン用語がわかる本 2004年版」(かんき出版)
「PC自作の鉄則!2005」「記録型DVD完全マスター2003」「買う!録る!楽しむ!HDD&DVDレコーダー」など(いずれも日経BP社)
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです