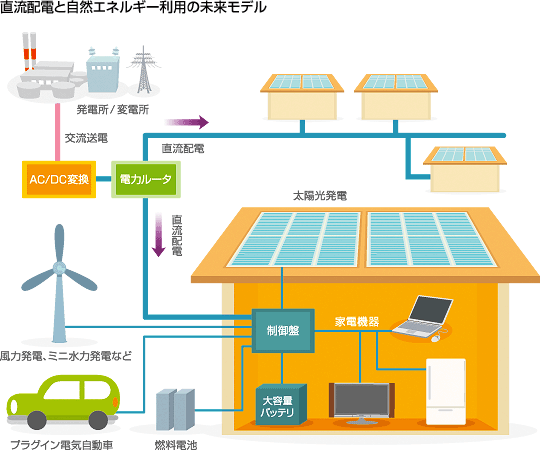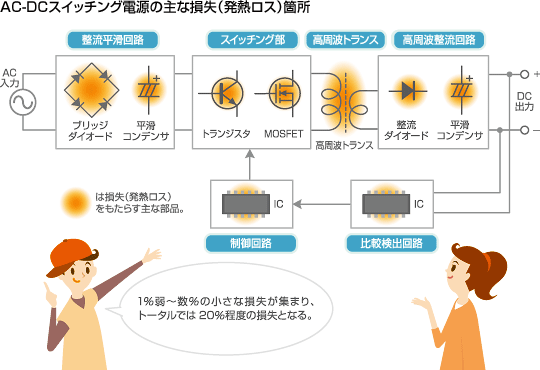パワーエレクトロニクス・ワールド
第4回 スイッチング電源を誕生させたパワーエレクトロニクスの技術史
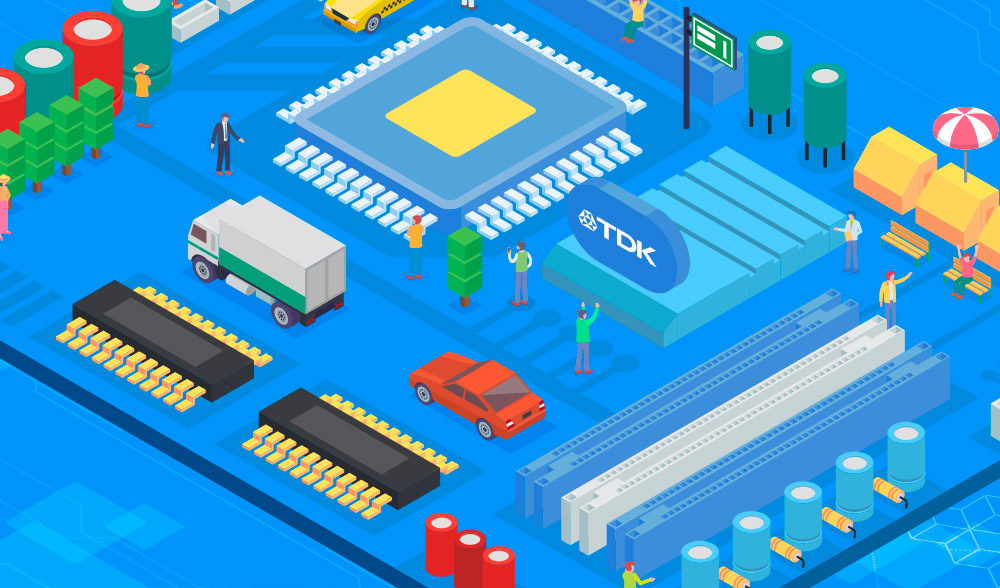
真空管ラジオや真空管アンプづくりが静かなブームとなっています。かつて“ラジオ少年”であった団塊世代が、定年を迎えていることも関係しているようです。20世紀半ばすぎまで、真空管はエレクトロニクスを推進した花形部品。商用交流を直流に変換する電源回路も真空管で構成されていました。20世紀に始まる電源進化は今なお続いています。
真空管から半導体素子、シリーズ電源からスイッチング電源へ
真空管はダイオードやトランジスタなどの半導体素子に置き換わりましたが、今日のパワーエレクトロニクスには真空管時代からのさまざまな技術が継承されています。ダイオードという名称も、もともと二極管(二極真空管)に由来します。
初の真空管である二極管は電球(白熱球)の実験がヒントとなって開発されました。1884年、エジソンは自ら発明した電球(白熱球)の改良を図るために、電球の中に電極を挿入して実験したところ、電極に正の電圧を加えると、空間を隔てて電極とフィラメントの間に電流が流れることに気づきました。これはエジソン効果と呼ばれます。エジソンは電球改良には役立たなかったので放置してしまいましたが、この現象に関心を示したのは、当時、エジソン電灯会社の技術顧問であったフレミング。彼は電極とフィラメントには一定方向の電流が流れることに着目し、無線通信の検波器(通信電波から信号を取り出す装置)として利用することを思いつきました。こうして1904年に発明されたのが二極真空管(ダイオード)です。ダイ(di)は“2”、オード(ode)は電気の通る“道”という意味からの命名です。
当初、検波器として用いられた二極管は、のちに整流回路にも用いられるようになりました。ラジオ放送が開始されたころの受信機は電池式でしたが、ひんぱんな電池交換が大変なので、商用交流を直流に変換する電源回路が搭載されるようになったからです(鉱石ラジオは電池なしに受信できましたがスピーカを鳴らせません)。下図に示すのは戦前・戦後まもないころの日本で使用された並三(なみさん)型や並四(なみよん)型と呼ばれた真空管ラジオの整流回路部です。重量・体積の多くが電源トランスと大容量の電解コンデンサ(平滑用コンデンサ)によって占められていました。
1950年代になると半導体素子であるダイオードやトランジスタが量産されるようになり、真空管方式の電源も“ソリッドステート”の時代に移行しはじめました。とはいえ電源の小型・軽量化はそれほど進行しませんでした。交流をまず電圧変換してから整流する従来方式では、やはり重くて大きな電源トランスや大容量の電解コンデンサを必要としたからです。また、トランジスタは真空管とちがって熱に弱いため、トランジスタの発熱対策として大きな放熱器も必要とされました
電源の小型・軽量・高効率化には、回路技術における画期的な革新が不可欠でした。おりしも当時は宇宙開発の開幕期で、宇宙機器に搭載するための新たな電源が求められました。このような背景の中から、アポロ計画を進めるNASAによって開発されたのがスイッチング電源です。
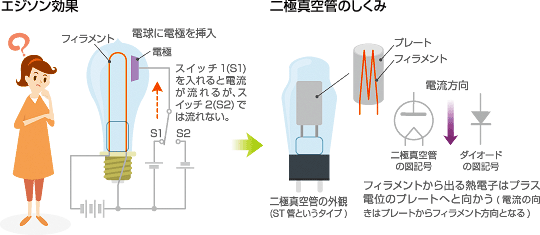
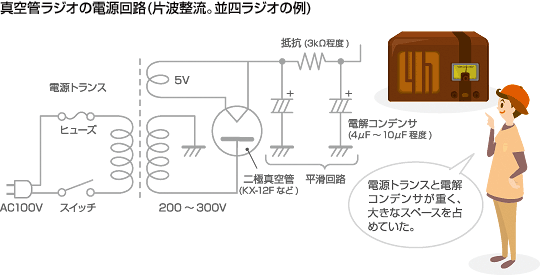
スイッチング電源はいわば電子機器の心臓
前号までにたびたびご紹介したように、スイッチング方式の電源は、トランジスタなどの半導体素子の高速スイッチング(ON/OFF)で出力を制御します。シリーズ方式ではトランジスタにたえず電流が流れているのに対して、スイッチング方式ではトランジスタがON時のみ電流が流れるので、無駄な電力消費が少なく効率化が図れるのです。
スイッチング方式そのものは、1950年代に考案されました。ただ当初は交流入力を電源トランスで電圧変換してからダイオードで整流し、これをスイッチングトランジスタでON/OFFして電圧変換する“シリーズスイッチング電源”と呼ばれるものでした。従来型のシリーズ電源より効率がよいとはいえ、やはり重い電源トランスを使うため、それほど軽量化は達成されませんでした。当然ながら次なる技術課題となったのがトランスの小型化です。トランスの大きさは1次巻線に送られる交流の周波数によって決まります。つまり、周波数を上げればトランスは小型のものですみます。そこで、交流入力をダイオードで直接整流したあと、トランスの1次側を高速スイッチングするという方式が考案され、そのための電力用高耐圧スイッチングトランジスタも開発されました。これによってトランスの小型・軽量化とともに、70%以上というすぐれた変換効率も実現できるようになりました。回路技術と半導体技術が、小型・軽量化・高効率化という電源ニーズに応えたわけです
今日、商用交流から必要な直流電圧を得る(ラインオペレート型という)スイッチング方式の電源は、一般に「スイッチング電源」とか「スイッチング・レギュレータ」などと呼ばれています。電子機器をロボットにたとえれば、スイッチング電源はその心臓といえます。ロボットの性能やパワーに応じて、心臓である電源もパーツのように選択・交換できれば便利です。そうした考えから量産される電源を「標準スイッチング電源」といいます。標準スイッチング電源が日本で開発されるようになったのは1970年代初頭。“インベーダーゲーム”などのコンピュータゲーム機の流行や自動販売機、パソコンなどの普及により、標準スイッチング電源の重要性は急速に高まり、小型・軽量・高効率化も著しく進行。当時のものと比べて、その大きさは10分の1以下まで小型化しています。また、ユニット型(カバー付タイプ、オープンタイプ)のみならず、機器に組み込む基板型(オンボード)スイッチング電源も、用途に応じたさまざまなタイプが提供されています。
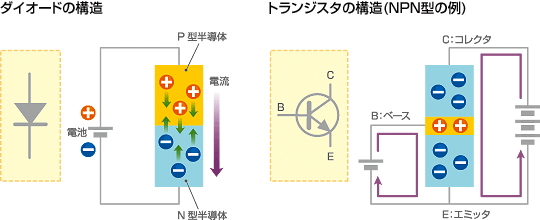
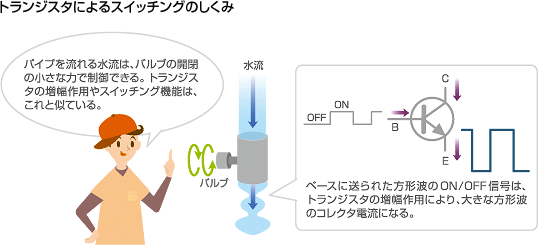
整流平滑回路にもきめ細かな工夫がほどこされている
スイッチング電源は、整流平滑回路、直流電圧を変換するDC-DCコンバータ、出力を検出・フィードバックして安定な電圧を得る安定化回路などからなります。さらなる効率化やノイズ抑制のため、スイッチング電源はこの基本回路に加えて、さまざまな回路技術が取り入れられています。たとえば整流平滑回路における突入電流制限回路もその1つです。
スイッチング電源の整流平滑回路は、コンデンサインプット型とチョークインプット型の2タイプがあります。ダイオードで整流したした直後の電流はまだ脈流です。これを平坦化するため、整流回路の直後に並列にコンデンサを入れるのがコンデンサインプット型です。コンデンサインプット型は簡便ですが、力率が低いという短所があります。力率というのは、皮相電力(電圧計と電流計の測定値の積)に対する有効電力の比率のこと。力率が低いと高効率化は望めません。
より平坦化を図るのがチョークインプット方式です。これは電流変化に対してブレーキをかけるよう作用するコイルの作用(自己誘導)を利用したもので、リップル電圧(さざ波状の電圧変動)を低くして力率を改善します。しかしチョークコイルが追加される分、電源の体積も重量も増してしまいます。このため、一般的なスイッチング電源ではコンデンサインプット方式が主流です(近年、この問題を解決するための力率改善回路を搭載した電源も増えています。これについては次号以降でご紹介します)
コンデンサインプット方式では突入電流に対する対策が重要になってきます。突入電流とは電源スイッチONとともに流れる瞬間的な大電流のこと。コンデンサインプット方式では、突入電流にほどよくブレーキをかけるチョークコイルをもたないため、コンデンサには急激に大電流が流れ込んでしまうからです。最も簡単なのは抵抗を直列接続する方式ですが、これは電力損失となるので小電力タイプのみにしか適用できません。一般にはサーミスタやサイリスタを用いた方式が採用されています。
サーミスタは温度上昇とともに電気抵抗値が下がる性質をもつ素子。突入電流が流れて温度上昇するにつれ電気抵抗値が下がるので、少ない電力損失で突入電流を抑制することができます。サイリスタ方式はサイリスタと抵抗を並列結合した回路。最初はサイリスタはOFFの状態で抵抗によって突入電流を抑制し、コンデンサの充電が終わる頃合に、サイリスタがONして抵抗の損失をなくすという方式です。このように突入電流制限という小さな回路にも、省電力・高効率化に向けた工夫が投入されています。パワーエレクトロニクスの奥深さの一端がご理解いただけたでしょうか?
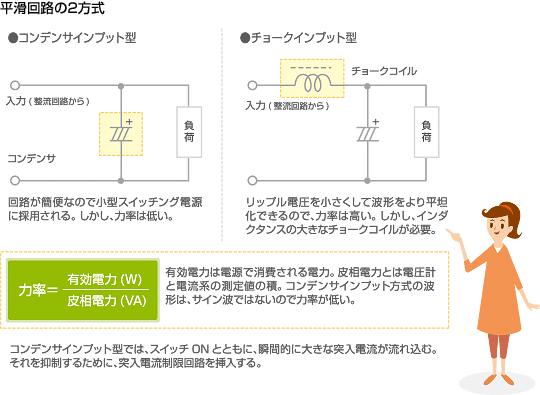
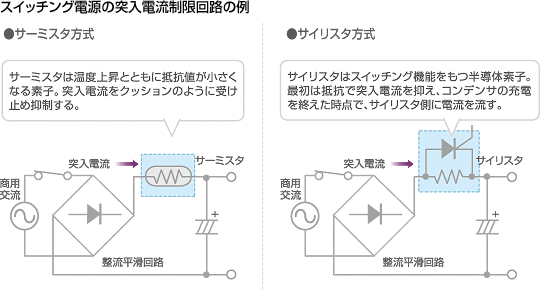
TDKは磁性技術で世界をリードする
総合電子部品メーカーです