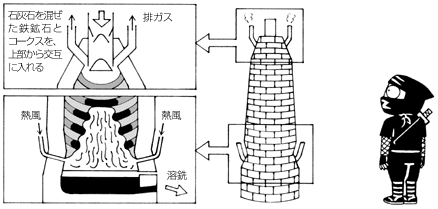じしゃく忍法帳
第86回「磁石のものさし“磁気スケール”」の巻

目には見えない縞模様
シャクトリムシという名前の由来
目で見ておよその量を見積もることを目分量といいます。忍法の1つである“山野の見積もり”とは、目分量で山の大きさや川幅、領地の広さなどを計測する術です。コツは基準となるものさしをイメージとしてもっておくこと。巨大な容積を表すのに、東京ドーム何杯分などというのと同じです。
比較的小さなものの長さを計るときには、手や腕がものさしがわりに利用されました。橋の支柱間の距離のことをスパンといいます。これはもともと古代エジプトにおいて、手のひらを広げたとき、親指と小指の間の長さをスパンと呼んだことに由来します。また肘(ひじ)から手の中指までの長さをキュビット、首の付け根から手の先までの長さをヤード、両手を広げたときの尋(ひろ)をファソムといいました。エジプトでは倍数法がとられ、2スパン=1キュビット、2キュビット=1ヤード、2ヤード=1ファソムとなっています。覚えておくと何かと便利です。
中国で使われた尺という長さの単位も、もともとは手のひらを広げたときの親指と中指の間の距離を意味しました。尺という字の“口”の部分が手のひら、“八”の部分は親指と中指を表しているといわれます。親指と中指を交互に運んで、1尺、2尺…と計測していく時の手の動きは、ある種のガ(蛾)の幼虫の歩き方に似ています。そこでこの幼虫はシャクトリムシ(尺取虫)と呼ばれるようになりました。

度量衡の基準器となった笛
手のひらの大きさは人によってまちまちです。そこで、中国では紀元前の昔からものさしを標準化するために楽器が用いられました。黄鐘(こうしょう)と呼ばれる鐘を鋳造し、その音に合わせた律管(笛)をつくり、その長さを基準としたのです。これを黄鐘管といいます。のちに主要農産物であるキビ(黍)も黄鐘管と対応させて利用されました。中サイズの秬黍(クロキビ)の粒の横幅を1分とし、10分で1寸、10寸で1尺とする単位系です。黄鐘管は90粒(9寸)の長さとされたので、これによって黄鐘管なしでも、全国的にほぼものさしが統一されることになりました(ただし、キビの縦幅を1分としたり、9寸を1尺、8寸を1尺とされたりしたので、尺の長さは時代によって異なります)。
多数の部品からなる工業製品においても、形状や寸法の規格化は不可欠の要件です。また、使用する材料や作業方法まで含めた共通の基準を設けることにより、分業もはじめて可能になり、生産効率も品質も向上します。これを標準化(standardization)といいます。
近代工業における標準化の始まりは、18世紀末にアメリカのホイットニーが小銃生産に取り入れたゲージシステムといわれます。ゲージとは物体の長さや大きさ、角度、形状などを測定するための器具のこと。いかにものさしが正確でも、ものさしや分度器の目盛を読みながら工作していては製品寸法にばらつきが生まれます。この問題を解決したのがゲージシステムです。一定規格のゲージを用意しておき、それをあてがいながら旋盤やフライス盤で部品を生産するという方式です。この画期的なアイデアによって、互換式の小銃が分業方式で大量生産できるようになりました。
磁気の縞模様をヘッドが読み取りデジタル表示
機械工学とエレクトロニクスが合体して、メカトロニクスという新たなテクノロジーが誕生した20世紀後半には、各種工作機械や産業機器にきわめて高度な位置決め技術が求められるようになりました。メカトロニクスを支えるのはセンサ技術とコンピュータ技術。そこで、何らかのセンサによってものさしの目盛を読み取り、これを電気信号としてコンピュータに送って機器を精密制御する技術が確立されました。
視覚的なものさしの目盛にかわって、磁石材料に微細な磁気パターンを記録し、それをものさしの目盛として利用したのが磁気スケールです。磁気スケールのつくり方は、磁気テープへの磁気記録と原理的に同じです。レーザ干渉計を用いて距離を精密に計りながら、リボン状のスケールベース(磁石材料)に記録ヘッドから正確なピッチで磁化していくのです。つまり、N極・S極が交互に並んだ微細な磁石の縞模様がものさしの目盛となります。
この磁気的な目盛を検出ヘッドで読み取り、電気信号に変換することで、1μm(マイクロメートル)あるいはそれ以下の距離の計測も可能になります。たとえば磁気変調方式磁束応答型と呼ばれるタイプは、図1に示すように基本的に2つの検出ヘッドによって読み取ります(複数のヨークをもたせて高精度にしたものはマルチギャップヘッドと呼ばれます)。2つの検出ヘッドは磁気スケールに記録された磁気の縞模様のピッチに対して、90゜位相がずれるように配置されているため、移動方向や移動距離、静止位置なども検出できるのです。検出ヘッドで得られた電気信号は、ディテクタの信号処理回路に送られ、これをカウンタ装置でデジタル表示されます。
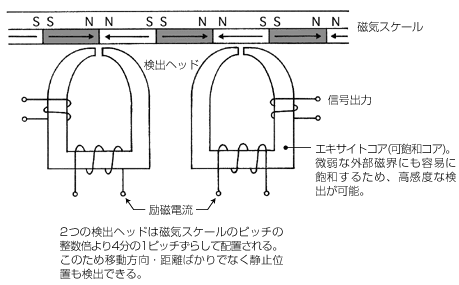
図1 磁気スケールと検出ヘッド(磁気変調方式磁束応答型)
プラスチック磁石を利用したロータリーエンコーダ
直線状の磁気スケールを回転体の周囲に据えると、回転角の計測するロータリーエンコーダとなります。たとえばしなやかな腕の動きを実現するロボットアームなどには、複数の関節ごとにロータリーエンコーダが必要となります。かつてロータリーエンコーダといえば、スリット円板とフォトICを組み合わせた光学式タイプが使われましたが、近年は耐久性にすぐれた磁気スケールとMR素子を用いたものが主流となっています。
MR素子のMRとは磁気抵抗効果(Magneto-Resistane Effect)の略語で、磁界が加わると内部抵抗が変わる特殊な素材(化合物半導体や強磁性体金属の薄膜など)を用いた磁気センサです。ロータリーエンコーダの磁気スケールには、自由な形状に成型できるプラスチック磁石が用いられます。このプラスチック磁石の磁気スケールをロータの周囲に巻き、ホルダ側の検出部にMR素子を配置すると、回転速度や回転方向、回転角などを検出することができるのです。磁気式エンコーダは光学式エンコーダと比較して、構造がシンプルで部品点数も少なく、振動にも衝撃にも強いため、モータと直結する工作機械などにはうってつけなのです。
正確な寸法取りはモノづくりの基本。磁気スケールは身の回りのいろいろな場面で使われるようになっています。たとえばDIY店などにいくと、大型のパネルソーが置かれていて、木材を所望の寸法にカットしてくれます。従来のように視覚で寸法取りすると1mm程度の誤差が出てしまいますが、磁気スケールを利用すれば、0.1mm単位の正確なカッティングも可能になります。模型工作などにもいろいろと活用できそうです。
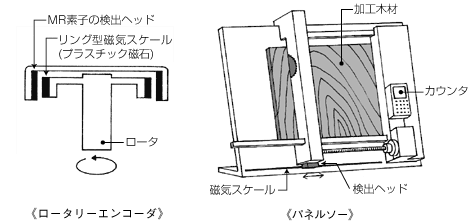
図2 磁気スケールの応用例
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです