じしゃく忍法帳
第85回「化学分析と磁石」の巻

化学におけるエレクトロニクス革命
音の蜃気楼現象
炎天下の砂漠や平原、アスファルト道路などにおいて、遠くに水たまりのようなものが見えることがあります。ところが、まるで神出鬼没の忍者のように、いくら近づいても水たまりなど見つけられません。これは“逃げ水”と呼ばれます。太陽光によって大地が強く熱せられると、地表付近で温度差の激しい空気層ができ、プリズムやレンズのような効果が生まれて光が屈折するのです。陽炎(かげろう)や蜃気楼と同様の現象です。
空気の振動によって伝わる音もまた、蜃気楼と似たような現象を起こします。たとえば、よく冷え込む夜間などに、遠くの電車の通過音や祭りの太鼓、お寺の鐘などが、ずいぶんと近くに聞こえることがあります。夜は騒音が少ないことも関係しますが、これは地面と上空との温度差が日中と異なることによるものです。
空気中を伝わる音の速度は気温と関係があり、331.5+0.61t(m/秒)という式で表されます。tは気温(℃)で、気温が高いほど伝わる速度も大きくなります。
日中は太陽光の照射によって地面が暖められるので、地表付近の気温は上空よりも高いのが通常です。しかし、晴天の続く晩秋などには、放射冷却によって夜間の地表付近の気温は、上空よりもぐんと低くなることがあります。このような場合は、音源から周囲に発した音は地上方向に曲げられます。ふだんは地上の遮蔽物にさまたげられてしまう音も、砲弾のようなカーブを描いて上空から届くため、遠くの物音が意外と近く聞こえるのです。
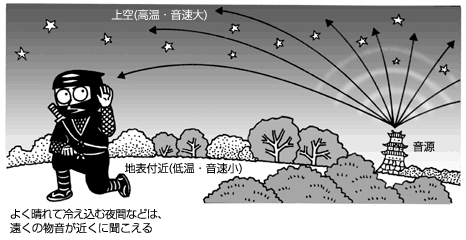
原子質量の測定法を一変させた分析機器
陰極線(電子線)も磁界によって軌道を曲げられます。磁界と電子の運動方向の双方に、ローレンツ力が垂直に作用するからです(フレミングの左手の法則)。一様な磁界に対して垂直に飛び込んだ荷電粒子は、このローレンツ力によって円運動(サイクロトン運動)をします。荷電粒子であるイオンもまた電子と同様に円運動するので、これを利用することでさまざまなイオンの質量を計測したり、その組成や構造などを調べることができます。これが質量分析計(MS=Mass Spectrometer)と呼ばれる分析機器の基本原理です。
質量分析計の開発の発端となったのは、19世紀末〜20世紀初頭における放射線の研究です。放射線にはα線、β線、γ線の3種がありますが、当初は2種類しか知られておらず、透過力の小さなものがα線、透過力の大きなものがβ線と名づけられました。α線もβ線も磁石の磁界によって曲げられます。しかし、曲がる方向は互いに正反対で、α線よりもβ線のほうが大きく曲がります。さまざまな実験結果から、β線は陰極線と同じ電子線であり、α線はヘリウムの原子核であることが突き止められました(のちに発見されたγ線は粒子線ではなく電磁波)。
電子にかぎらず電荷をもつ粒子は、磁界中でその質量に応じた曲がり方をすることがわかったのもこのころです。1910年代になると質量分析計の原型ともいうべき装置が考案され、原子質量や同位体元素の存在比の測定などに使われるようになりました。化学反応によって目的成分を分離・沈殿させ、それを乾燥・秤量してきた従来の化学的手法と異なり、質量分析は微量の試料でも高精度に測定できる画期的な分析法でした。
質量電荷比に応じて物質をふるいわけ
最も基本的な質量分析計(単収束扇形磁界型)の構造は、試料をイオン化して放出するイオン源、磁界を発生するアナライザ、検出器からなります(図1)。加速電圧をかけられてイオン源から飛び出したイオンは、扇形のアナライザの磁界中で円弧を描きますが、このときの曲率半径rは、質量電荷比 m/zeに比例します(mは質量、zは電荷数、eは電気素量)。つまり、質量電荷比が大きいイオンほど曲率半径rは大きくなるため、磁界の強さを連続的に変えてやることで、質量電荷比 m/zeの質量スペクトルが得られます。
しかし、同種のイオンでも速度が異なると検出部にはバラバラに飛び込んでくるため、分解能が悪くなります。そこでイオンに静電界や、直流と高周波交流を重ねた電圧を加えてイオンを収束させる技術も開発されました。二重収束型、四重極型と呼ばれる質量分析計です。これは光学顕微鏡にたとえれば収差を少なくする工夫です。また、イオンが通過する時間が、m/zeの値によって異なることを利用した飛行時間型と呼ばれるタイプは、きわめて高感度の質量分析を実現します。
このように質量分析計は各種タイプがありますが、いずれもイオンをその化学的性質ではなく、質量電荷比によってふるい分けする装置です。このため、複雑な混合物などでは異なる物質を識別することが難しくなります。そこで、イオン化する前にある程度、試料を分離しておく必要があり、ガスクロマトグラフィ(GC=Gas Chromatography)と連動させた装置が主流となっています。この質量分析計はGCMSと呼ばれます。
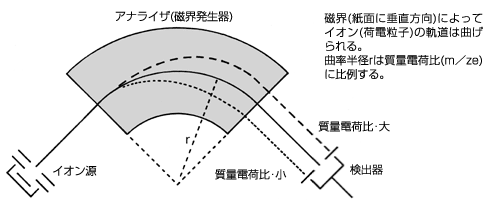
図1 質量分析計(単収束扇形磁界型)の基本構造
ノーベル化学賞を受賞した質量分析の新手法
従来、質量分析計は原子質量の測定などには威力を発揮するものの、高分子の有機化合物の分析は苦手でした。イオン化するとき結合が切れてバラバラになったりするからです。低分子の有機化合物ならバラバラになった断片を測定し、そのデータから元の化合物を推定することも可能ですが、タンパク質のような高分子では、たとえていえばシュレッダーにかけた本をつなぎ合わせて復元するようなもので、とても困難だったのです。
この問題をみごと克服したのが、2002年のノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏です。「生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」というのが受賞理由で、「マトリックス支援レーザ脱離イオン質量分析法」の開発が田中耕一氏の受賞対象となりました。
これはマトリックスと総称される特殊な化合物と試料の混合物をつくり、そこにパルスレーザを照射する手法。パルスレーザによってマトリックス物質を気化させると、タンパク質のような有機高分子も分解されることなくイオン化されるのです。試料そのものが直接加熱されないため、これは“ソフトなイオン化”と呼ばれます。マトリックスには各種あり、それぞれ固有の吸収波長をもっているため、分析対象物の違いによってマトリックスを使い分けたり、照射するレーザの波長も切り替えます。この新装置の開発によって、さまざまな有機高分子も、きわめて高効率・高精度に質量分析できるようになり、タンパク質の構造解析や新薬開発などに大革新がもたらされました。
質量分析計は化学、物理、エレクトロニクスのインテグレーションによって大きく進化を遂げたハイテク機器。近年は、超電導磁石を利用したFTMS(フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計)と呼ばれる超高性能の質量分析計も開発されています。タンパク質工学やライフサイエンスの分野においても、磁石とエレクトロニクス技術はますます活躍の場を広げそうです。
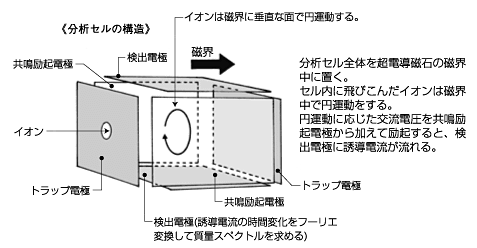
図2 FTMS(フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質量分析計)の原理
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです







