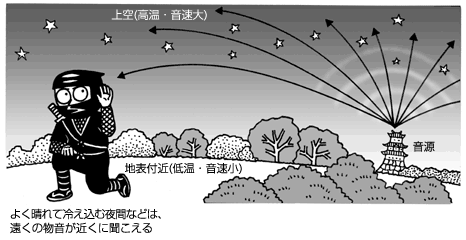じしゃく忍法帳
第84回「電子顕微鏡の電子レンズ」の巻

ナノスケールのフロンティアを探る
日本人はいつからメガネをかけたか?
「火のないところに煙は立たぬ」といいますが、野菜づくりなどに使うビニールハウスで、ときどきミステリーまがいの火事騒ぎが起こることがあります。犯人はビニールハウスの上にたまった雨水。ビニールはたわむので、たまった雨水は凸レンズ状になります。これが太陽光を収束させ、焦点を結ぶところに可燃物があると発火させてしまうのです。同様にガラスの花瓶や金魚鉢、ペットボトルなども、凸レンズと同じ効果を示すので注意が必要です。ましてや凸レンズそのものである老眼鏡や天眼鏡、ルーペなどは、窓際に放置してはいけません。
太陽光を集めるために使われる凸レンズは、江戸時代の日本では「火珠(ひとりだま)」と呼ばれました。もともとは透明な水晶を磨いて片側を平らにし、もう片側を球面にしたものですが、江戸時代の百科事典『和漢三才図会』(1712年刊)では、「近年、火珠にはビイドロ(硝子)を用い、平たくてメガネのようなものもある」ということが記されています。
日本人がメガネを知ったのは戦国時代。ポルトガル船に乗って来日したフランシスコ・ザビエルが、1551年に周防(現・山口県)の武将・大内義隆に献上したものが最初といわれます。ガラスを意味するビイドロはポルトガル語ですが、レンズはオランダ語です。江戸に幕府が開かれて鎖国時代になってもオランダとの貿易は行われました。当時、オランダはレンズ技術の先進国。最新のレンズ技術は日本にももたらされ、江戸時代には老眼鏡、近眼鏡ばかりでなく、遠眼鏡(望遠鏡)や顕微鏡も製作されていたのです。

ミクロ世界の扉を開いた単眼式顕微鏡
2つのレンズを組み合わせると拡大率が相乗的に大きくなることは、1590年ごろ、オランダの眼鏡師ヤンセン父子によって、偶然、発見されたといわれます。ヤンセン父子は接眼レンズと対物レンズを用いた初の複式顕微鏡を発明し、ほどなく同じ原理によって望遠鏡も発明されました。
ところが、当時、光学理論は未発達で、複式顕微鏡では収差(色収差や球面収差)の問題がつきまといました。色収差とは波長によって屈折率が異なるため、正確に像が結ばない現象。一方、球面収差とはレンズ中心部と周辺部の屈折率の違いにより、周辺がボケてしまう現象です。17世紀半ば、オランダのアマチュア顕微鏡学者レーヴェンフックは、血液細胞や原生動物、ヒトの精子などを観察し、ミクロ世界の扉を開きましたが、彼が自作して使ったのは、驚くほどシンプルな単眼式顕微鏡でした。
レーヴェンフックの単眼式顕微鏡は1個のレンズを2枚の真鍮板ではさんだ簡単な装置。真鍮版には小さな穴があけられていて、そこからレンズが拡大する像をのぞく仕組みです。原理的にはルーペ(虫メガネ)と同じですが、この装置のミソは直径数mm程度の小さなガラス球をレンズとして使うところ。ガラス球の直径を小さくすると焦点距離は短くなるものの、拡大率は大きくなるのです。18世紀から19世紀かけて、収差をなくした複式顕微鏡が発明されるまで、実用的な顕微鏡としては、もっぱら単眼式顕微鏡が使われました。
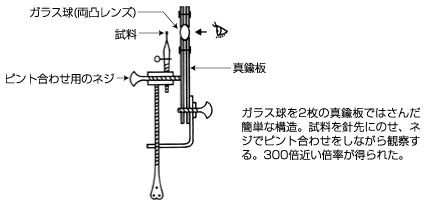
図1 レーヴェンフックの単眼式顕微鏡
コイルの磁界で電子線を収束する
光学顕微鏡ではいくら倍率を高めても、数100nm(ナノメートル)が分解能の限界となります。これはレンズの性能によるものではなく、可視光の波長が380〜800nmであることに原因します。
よく知られているように、電子は粒子であるとともに波としての性質をもちます。そこで、光の波のかわりに電子の波を利用したのが電子顕微鏡です。
磁界中を運動する電子にはローレンツ力が作用して軌道が曲げられます。この現象を応用して19世紀末にはブラウン管が発明され、1920年代には通信技術と結びつけてテレビの研究も世界的に進められました。ちょうどそのころ、光を陰極線(電子線)に置き換えれば、電子レンズが可能になることがドイツのブッシュによって理論的に指摘されました。
電子顕微鏡には磁界型という電子レンズが使われます。これは簡単にいうと電流を流したドーナツ型のコイルです。磁界に平行して進入する電子は直進しますが、磁界に直交する電子は円軌道をとり、斜めに進入する電子はらせん軌道をとります。しかし、単にコイルの中に電子線を通しただけでは、電子線は収束させることができません。
そこで考えられたのが、コイル全体を軟鉄製のヨークで覆い、コイル内部にカメラの絞りのようなポールピースを設けた構造の電子レンズ。コイルが発生した磁束はポールピースの先端に集まるように工夫されているので、電子銃から照射された電子ビームは細く絞られ、ある距離で焦点を結ぶことになります。この電子レンズを2段に据えて、初の電子顕微鏡を発明したのはドイツのルスカです。1940年前後には分解能5〜10nmの実用的な電子顕微鏡も販売されるようになりました。
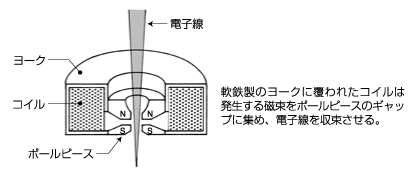
図2 電子レンズの構造
走査型プローブ顕微鏡(SPM)
ルスカが発明したのは透過型電子顕微鏡(TEM)と呼ばれるタイプで、薄片にした試料しか観察できません。一方、ルーペで物体を拡大するように、立体的な試料をそのまま拡大して見せるのが走査型電子顕微鏡(SEM)。試料に電子線を走査して、飛び出す2次電子をとらえて画像化する装置です。2次電子の発生量は試料の凹凸によって異なります。一般に試料の平坦部より傾斜部や突起部などのほうが、2次電子の発生量が多くなるため、これを検出器でとらえて電気信号に変えることで、濃淡のある立体的な画像が得られるのです。また、試料に電子線を照射すると、2次電子のほかにX線や光なども飛び出します。これらを情報として利用したものは分析電子顕微鏡と呼ばれます。
1980年代には走査型トンネル顕微鏡(STM)という新たな原理による顕微鏡も発明されました。STMには電子レンズのようなものはなく、そのかわり微細な金属針が使われます。金属針を試料に至近距離まで近づけると、量子力学的なトンネル効果(十分なエネルギーをもたない電子が、エネルギー障壁をすりぬける現象)により、トンネル電流という電流が流れます。このトンネル電流が一定になるように金属針を移動させると、試料表面の状態を知ることができるというのがその原理。従来の顕微鏡が視覚的な機器だとすると、STMは微細な針で試料をなぞる触覚的な機器です(ただし非接触)。
STMは1nm以下という原子サイズの分解能をもつため(水平分解能は約0.2nm、垂直分解能は約0.01nm)、金属やセラミックスの微細構造も高精細に観察できるようになりました。また、STMの開発後、原子間力や磁力などを検知しながら走査する原子間力顕微鏡(AFM)や磁気力顕微鏡(MFM)なども開発され、これらは走査型プローブ顕微鏡(SPM)と総称されています。ナノスケールの未知のフロンティアにおいて、今後、どんな発見・発明がなされるか楽しみです。
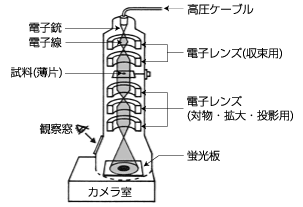
図3 電子顕微鏡(透過型)の構造
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです