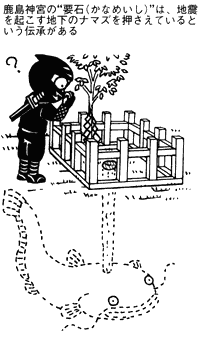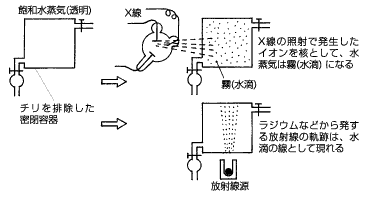じしゃく忍法帳
第77回「宇宙ロケットと磁石」の巻

火星旅行を目指すプラズマロケット
忍者が使ったポータブルな大砲
長篠の戦(1575)において、織田・徳川の連合軍が、3500挺の鉄砲で武田軍を撃退したのは有名な話です。種子島に鉄砲が伝来したのは1543年。実戦に使われだしたのは1550年前後。わずか30年で合戦の形態は大きく様変わりしました。
鉄砲の伝来以後、火薬を用いた各種の火器も考案され、忍者はノロシや煙幕、手投げ弾のほか、携帯用の大砲も用いたといわれます。これは軽い桐(きり)の材で木筒をつくり、その周囲を銅線でぐるぐる巻きにしてから、美濃紙などの丈夫な和紙で練り固めたもので、“張子筒(はりこづつ)”などと呼ばれました。重さは数10kg ほどなので、鋳物の大砲とくらべると運搬がはるかに容易。城攻めや近距離の敵を攻撃するのに威力を発揮したといわれます。
火箭(かせん)”とか“火矢(ひや)”と呼ばれるロケット弾も使われました。ただし、これは日本の発明ではなく、11世紀中国(宋代)の軍事技術書『武経総要(ぶけいそうよう)』に、すでに掲載されています。鎌倉時代に日本に来襲したモンゴル軍も使用したと伝えられています。現在の“ロケット花火”と大差ないものですが、これがロケットの先駆といわれます。
ロケットは積載した推進剤の燃焼ガスの噴出で飛行します。地上すれすれに飛んでいく巡航ミサイルもありますが、推進剤がなくなれば当然ながら地上に落下してしまいます。しかし、飛行速度が毎秒7.91kmとなると、地球の引力と遠心力がつりあうため、推進剤なしに地球を周回するようになります。人工衛星の打ち上げに必要なこの速度を第1宇宙速度といいます。もちろん、これは大気の抵抗を無視した場合です。大気圏でこのような高速飛行はできないので、ロケットは徐々に加速し、大気の影響のない高度に達してから、人工衛星を軌道上に誘導するのです。
人工衛星は地球の中心を1つの焦点とする楕円軌道を描いて周回しますが、もっとスピードを上げて秒速11.18kmに達すると、軌道は楕円から放物線に変わって地球を飛び出し、太陽を周回する人工惑星となります。これを第2宇宙速度といいます。さらに秒速16.65kmの第3宇宙速度に達すると、軌道は双曲線となって太陽系の重力圏から抜け出し、銀河系の中を飛行するようになります。
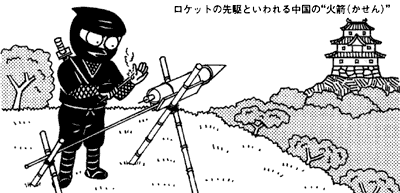
惑星の重力を利用するスイングバイ方式
現在のロケットの主流は、推進剤を化学的に燃焼させ、発生するガスを噴射して飛行する方式です。これは化学ロケットと呼ばれ、推進剤が液体の場合は液体ロケット、固体の場合は固体ロケットと呼ばれます。
推進剤の重量の占める割合は、ロケット全体の90%以上にも及びます。卵の白身と黄身を推進剤とすると、ロケットの機体は殻の重量よりも軽いことになります。また、通常の化学ロケットは単段では第1宇宙速度に達することができません。そこで、多段式として、下段を次々と切り離しながら加速します。いわば下段を蹴飛ばして加速するわけです。
航空機のように水平離着陸する単段のスペースプレーン(宇宙往還機)が理論的に可能なのは、大気中の酸素を酸化剤として利用するからです。
1977年に打ち上げられたNASAの惑星探査機“ボイジャー2号”は、木星を探査したあと土星、天王星、海王星へと飛行して、貴重な映像を地球に送り届けました。積載できる推進剤にはかぎりがあるので、ボイジャー2号では惑星の重力を利用して加速し、軌道変更する方式がとられました。これをスイングバイ航法といいます。当時、たまたま太陽系の外惑星が直線的に並ぶ時期だったので、これをうまく利用したのです。しかし、このようなつごうのよい惑星配列は176 年に1回しか巡ってきません。そこで、有人惑星探査をはじめとするこれからの宇宙開発を視野に入れて、化学ロケットにかわる高速・省エネ・高効率の新型ロケットの研究が進められています。
人工衛星の姿勢制御に使われるプラズマロケット
化学ロケットにかわるロケットはさまざまなタイプが考えられていて、それらは非化学ロケットと総称されています。大きな帆をつけて太陽風で運ばれる太陽帆ロケット、核分裂や核融合反応を利用したロケット、物質と反物質を反応させて光に変換し、それを噴射して推進する光子ロケットなどです。そのほとんどは構想段階にとどまりますが、プラズマロケットと呼ばれる電気ロケットは、すでに衛星の姿勢制御などに応用されていて、有人火星探査のロケットとしても有望です。
推進剤を高温に加熱すると、正負の荷電粒子が共存したプラズマ状態になります。これを高速噴射して推力を得るのがプラズマロケットです。最も簡単なのはアーク溶接機でおなじみの直流のアーク放電を利用したタイプ(図1)。アーク放電によって推進剤の気体を加熱し、生成した高温高圧のプラズマをノズルから噴射する方式ですが、アーク放電による電極消耗が避けられません。
この問題を解消できるのが、電磁力を利用した電磁加速プラズマロケット。プラズマの流れは磁界との作用でローレンツ力が発生します。このローレンツ力でプラズマを加速してから、いっきに噴射するのが電磁加速プラズマロケットの原理です。
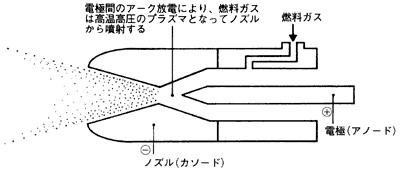
図1 直流アークジェット式プラズマロケットエンジンの構造
有人火星探査に向けたNASAの“VASIMR”
NASAで開発が進められている“VASIMR”は、有人火星旅行を目指した最新の電磁加速プラズマロケットです。VASIMRとは“可変特殊インパルス電磁プラズマロケット”の略語。図2に示すように、ドーナツ状の3つの超電導磁石を貫通するパイプの中に、水素またはヘリウムのガスが送られる構造となっています。超電導磁石による強力な磁界の中に加熱したプラズマを閉じ込め、そのエネルギーを後段の超電導磁石の後ろに設けた磁気ノズルからいっきに解放し、高速のプラズマ流として噴出するというのがその基本的な仕組み。従来の電磁加速プラズマロケットと違って、パイプを取り巻くアンテナから放射される電波によってプラズマが加熱されるので、電極消耗の問題がありません。また、推力を調節できる可変型であるため、きわめて効率がよいのも特長。
VASIMRは核融合反応を実現するためのアプローチの1つである“磁場閉じ込め”の技術から生まれたものです。化学ロケットにおける推進剤の燃焼温度は数1000Kですが、核融合の実験装置のプラズマ温度は数100万から1000万Kにも及びます。このような高温に耐える材料はないため、磁界によって高温プラズマを宙に浮かすのが“磁場閉じ込め”方式です。
現在の化学ロケットでは火星まで、片道でも7〜8か月もかかります。途中はエンジンを停止した慣性航行をするためです。しかし、VASIMRは効率的な加速航行ができるため、所要期間は半分以下の3か月に短縮できると計算されています。とはいえ、電磁加速プラズマロケットは電気ロケットの1タイプであり、有人火星探査となると10メガWもの電力が必要となります。これを現在の太陽電池でまかなうとなると、約250m四方の面積になるため、高効率の太陽電池パネルも求められています。
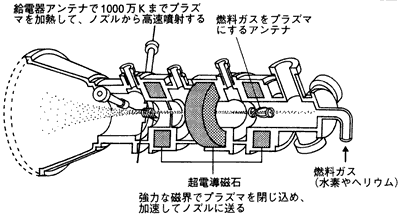
図2 NASAの電磁加速プラズマロケット(VASIMR)エンジンの構造
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです