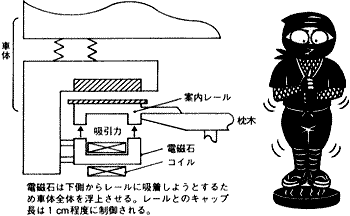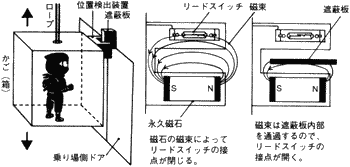じしゃく忍法帳
第60回「強磁場(強磁界)の利用技術」の巻

超電導マグネットをしのぐ強磁界発生装置
自然界の物質の多くは非磁性体
体をバラバラに切断すると、それぞれの破片が個体となって殖えるという、まるで忍法の“分身の術”のような再生力をもった生物がいます。河川や湖沼に生息するプラナリアという体長3cmほどの扁形動物です。
磁石はこのプラナリアのように、切っても切っても磁石としての性質を失いません。しかし、物質は原子・分子からなるので、磁石をどこまでも小さく分割することはできないはずです。そこで、19世紀の終わりごろ、磁石の最小単位として“分子磁石”というものが仮想されました。磁石というのは、目に見えない小さな分子磁石の集合体と考えたのです。
20世紀になって原子構造が解明されると、磁性のルーツは原子の磁気モーメントにあることがわかりました。このうち磁石の磁性に関与してくるのは、主に電子のスピン磁気モーメントです。結局のところ分子磁石というものは存在しませんでしたが、“電子磁石”ともいうべき電子のスピン磁気モーメントの集まりが、マクロの磁性となって現れていたのです。しかし、これで磁石の謎がすっかり解かれたわけではありません。
2本の棒磁石を束ねるとき、同極どうしをそろえると反発し合ってうまくいきませんが、異極どうしをそろえると、互いに吸いついて合体します。物質はエネルギー状態が最も低い状態で安定しようとする傾向があるからです。それと同様に、ミクロの電子磁石もまた、スピンが逆向きの相手を見つけ、安定しようとします。ペアを組むと磁石としての性質は相殺されてしまうため、自然界の物質のほとんどは、磁石に吸着しない非磁性体(弱磁性体)となっています。
しかし、例外的に鉄、コバルト、ニッケルなどの一部の原子は、ペアを組まない不対電子(磁性電子)が、原子軌道上でスピンの向きをそろえて配置しているため強磁性体となります。当然ながら、これらの不対電子には磁気的な反発があるはずです。原子という極小世界において、複数の不対電子が互いに反発しながら共存できるのはなぜでしょう?
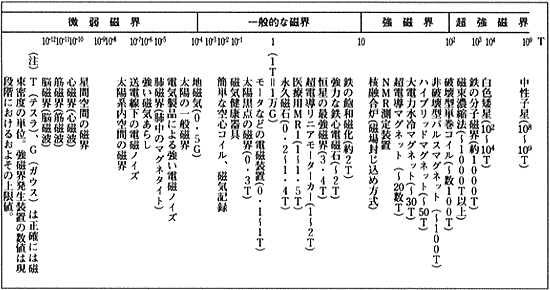
表1 さまざまな磁界とその強さ
強磁性を生み出す1000Tの分子磁界
この難題を分子磁界(分子磁場ともいう。磁界は磁場の工学用語)という概念の導入で解いたのはフランスの物理学者ワイスです(1907年)。彼は強磁性体の内部には、ミクロの磁石を同じ向きに並べようとする強力な磁界が存在すると考えました。強磁性体の科学は、ワイスのこの先見的な着想から発展を遂げたのです。
鉄の分子磁界の強さは約1000T(テスラ)と計算されています。これは白色矮星の磁界とほぼ同じ強さです。白色矮星とは太陽ほどの質量をもった恒星が、地球ほどの大きさに縮んでできた天体です。ちなみにパルサーとして観測される中性子星の磁界は、1億〜10億Tにも及びます。最も強力な永久磁石で約1.4Tですから、想像を絶するほどの強磁界です。
永久磁石の強さに上限があるのは、いかなる磁性体にも、磁気的な飽和状態というものがあるからです。磁性体を構成する原子の磁気モーメントがすべてそろってしまうと、それ以上、磁化が進行しなくなるのです。電磁石の磁心に電磁鋼などが使われるのは、こうした高透磁率の軟磁性材料が、ちょうどスポンジが水を吸うように、磁束をよく吸収するからです。しかし、スポンジの吸収量には限界があるように、コイルに流す電流が大きくなるにつれ、磁心もやがて磁気飽和状態に達します。
そこで、永久磁石や通常の電磁石で得られないような強磁界(約2T以上)を発生させるためには、磁心のない空心コイルが用いられます。空心コイルはエネルギー効率が悪いものの磁気飽和がないからです。
超電導マグネットというのも、超電導材料の空心コイルを用いた電磁石の一種です。ただし、超電導という物理現象には臨界磁界や臨界電流というものがあり、それを超えると超電導状態が破れてしまいます。電気抵抗がゼロであった超電導コイルは、一転して電気抵抗体となり、流れている大電流によってジュール熱が発生し、コイル全体が破壊されてしまいます。これをクエンチといいます。このため、超電導マグネットの発生できる磁界は、今のところ20数Tが上限となっています。
最強の定常磁場をつくるハイブリッドマグネット
超電導マグネットを上回る強磁界の発生装置としては、次のようなものがあります。
大電力水冷マグネットは、電気抵抗が小さく、強度にすぐれた導体(銅や銀などの合金)で空心コイルをつくり、コイル全体を水に浸けて冷やした装置です。電力の多くがジュール熱として奪われてしまいますが、水冷によって大電流が流せるので、30Tくらいまでの強磁界がつくれます。また、この大電力水冷マグネットと超電導マグネットとを組み合わせた装置は、ハイブリッドマグネット(図1)と呼ばれ、40Tを超えるものが実現しています。
100T以上の超強磁界を定常磁場として持続的に発生できる装置は、今のところありません。ただ、瞬間的なパルス磁界ならば、次のような方法で実現することができます。
その1つは、単巻(1回巻)コイルに、巨大容量のコンデンサから数100万アンペアの大電流を瞬間放電させる方法です。単巻コイルというのは、断面がヘアピンのような形をしたコイルらしからぬコイルです。このコイルに数100万アンペアもの大電流を流すと、金属製のコイルは一瞬のうちに溶けてしまいます。しかし、このとき円筒部には円電流が流れるので、溶ける直前に瞬間的に強いパルス磁界が得られます。とはいえ実験のたびにコイルを取り替えるのは不便です。そこで、繰り返し実験でき るように、ソレノイドコイルをエポキシ樹脂などで補強した非破壊型パルスマグネットというのも利用されています。
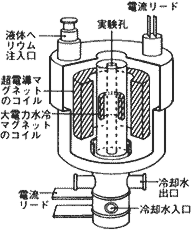
図1 ハイブリッドマグネットの構造
単結晶や薄膜の製造にも期待される強磁界の利用
数100〜1000Tもの超強磁界の発生には、磁束濃縮法という方法が使われます。これは金属円筒の中に磁束を通過させた状態で、金属円筒を電磁力や爆薬などで圧縮する方法です。図2に示したのは電磁力を利用した磁束濃縮法の原理です。金属円筒が瞬間的に圧縮されるため、金属円筒内部の磁束は外側に漏れ出すことができず、きわめて高密度な磁束が得られます。
こうした100T以上の超強磁界は主に実験・研究用で、装置も大がかりなものとなります。しかし、数T〜10数Tの強磁界なら、近年、比較的容易につくりだせるようになり、産業面での応用にも期待がかけられています。たとえば鉄鋼生産において、良質・均一な結晶状態をつくるために必要な溶融鉄の位置や速度の微妙な制御も、磁力ならば非接触で実現できます。また、単結晶や薄膜などの製造工程に、強磁界による磁気処理を応用しようという研究も進められています。強磁界の応用は始まったばかりの段階。画期的なエレクトロニクス材料が開発される可能性もあります。
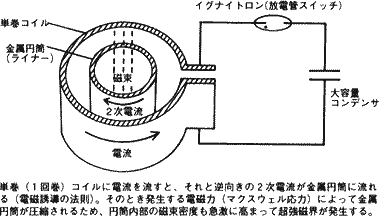
図2 磁束濃縮法(電磁力による)の原理
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです