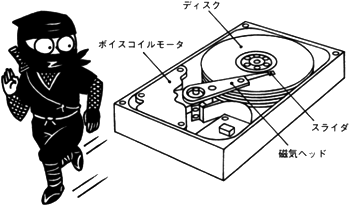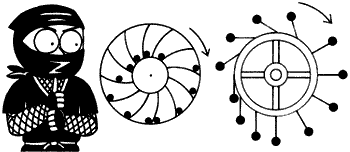じしゃく忍法帳
第57回「有機磁石は可能か?」の巻

有機物・無機物の“機”の意味は?
たえず機をうかがい、機転をきかして、機敏に行動するのが忍者。臨機応変こそ忍法の基本です。ところで、ふだん多用しながら、その意味があまり意識されないのは“機”という字。訓読みでは機(はた)ですが、もともとは弩(いしゆみ)の引き金を機といい、転じて物事の仕組み・からくり(機械や機構など)、きっかけ・きざし(機会、動機など)などを意味するようになりました。
「機によりて法を説く」という仏教のことわざもあります。この機は、人の心のはたらき(機能)のこと。仏の教えに感応する心のはたらきは、人それぞれに異なるので、お釈迦様は弟子の機に応じて適切な説法をしたと伝えられます。
自然界の物質は無機物・有機物に二分されますが、この場合の機は生命のはたらきという意味です。
鉱物などは生命機能がない物質であるため無機物とされ、動植物やその産物は有機物とされたのです。
かつてはいかなる有機物も人工的に製造できないものと考えられていました。ところが、1828年、ドイツの化学者ウェーラーは、単純な無機化合物であるシアン酸アンモニウムの水溶液を加熱すると、有機物である尿素ができることを発見しました。これが有機合成化学の始まりで、以後、有機体を起源としない有機化合物が続々と合成されるようになりました。もともと有機物と無機物を二分する本質的な境界などなかったのです。
それならば磁石もまた無機物とはかぎらず、有機物の磁石も存在するのではないでしょうか? ここで誤解しないでいただきたいのは、身の回りに多用されているプラスチック磁石やゴム磁石は、無機物であるフェライト磁石や希土類磁石の粉末をプラスチックやゴムに混練したもので、純然たる有機磁石ではないということです。有機磁石とは炭素−炭素結合を骨格とする有機分子そのものに磁性体として性質をもたせようというものです。はたして、そんな磁石が可能なのでしょうか?
電子材料にも使われる機能性高分子とは?
特殊な物理・化学的機能や生体類似機能をもたせた有機化合物のことを機能性高分子といいます。機能性高分子はすでに電子材料としても使われています。たとえば、ロボットの触覚センサには圧電性高分子、視覚センサには焦電性高分子などが利用され、液晶もまた電界により光学的性質を変える機能性高分子です。
金属なみの導電性をもつ機能性高分子も開発されています。電流とは電子の流れのことですが、有機物を特徴づける炭素−炭素結合に電子が局在化しているため、金属のような自由電子は存在しません。プラスチック類が電線の被覆に用いられるように、有機高分子は一般に絶縁体であるのはこのためです。特殊な有機高分子でもせいぜい半導体にしかなりません。
炭素−炭素結合に局在化した電子はσ(シグマ)電子と呼ばれます。有機物にはこのσ電子のほかに、π(パイ)電子と呼ばれるやや動きやすい電子があります。たとえばベンゼン環の二重結合はπ電子によるものです。このπ電子も通常は電流の担い手にはなりませんが、ある種の有機高分子にヨウ素などをドーピング(添加)すると面白い現象が起きます。ヨウ素が電子受容体(電子を受け取りやすい物質)となってπ電子を受け取り、導電性を示すようになるのです(図1)。
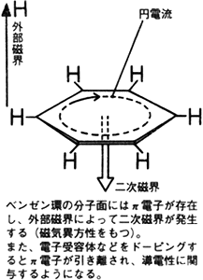
図1 ベンゼン環のπ電子
不対電子の存在は磁性体の必須条件
機磁石というのは磁性をもつ機能性高分子のことです。
物質の磁性の起源をミクロに追求していくと、主として電子のスピン磁気モーメントにたどりつきます。
スピン磁気モーメントによって、孤立した電子がミニ磁石としての性質をもつのは、スピン磁気モーメントによるものです。この孤立した電子のことを不対電子といいます。ただし、不対電子のミクロの磁性がマクロの強磁性(磁石となったり、磁石に吸着したりする性質)を発現するには次のような条件を満たす必要があります。
電子軌道の不対電子の存在
交換相互作用がはたらく原子配列
強磁性は量子力学的な原子間の協力現象である交換相互作用によって生まれます。このため、不対電子に交換相互作用がはたらくようなころあいの距離に原子が配列していることが必要です。
安定した磁気的構造
不対電子のスピン磁気モーメントの向きを統一するために、安定した磁気的微細構造も必要です。
鉄、コバルト、ニッケルが強磁性体となるのは、上記の1,2,3,の条件を満たすからです。鉄原子は4個、コバルト原子は3個、ニッケル原子は2個の不対電子をもち(条件1)、その金属結晶はころあいの原子配列をもち(条件2)、また磁区と呼ばれる安定した磁気的構造をもつからです(条件3)。
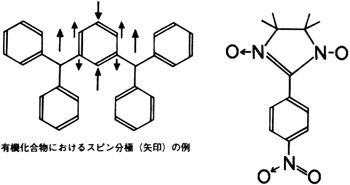
図2 初の有機磁石 p-NPNNの化学式
10年前に発見された世界初の有機磁石
有機化合物でも、上記の3条件をもたせられれば磁石となると考えられます。ところが、有機化合物においては構成原子の電子が2個ずつ対になって安定な共有結合をつくっているので、とても磁性材料となりそうにもありません。ただ、化学反応の過程においては、この共有結合が壊れてラジカル(フリーラジカル、遊離基)と呼ばれる反応中間体が生成されます。ラジカルは孤立した不対電子をもつため磁性を示します。
反応中間体としてのラジカルは不安定で短時間の寿命しかもちませんが、安定した有機ラジカル分子を利用すれば、有機磁石が実現できそうです。ラジカルの不対電子のスピンの向きがバラバラだと常磁性という弱い磁性しか示しません。しかし、分子間でうまくスピンをそろえられれば、強磁性的な性質をもたすことができると考えられるからです。
初の有機磁石は1991年、東京大学物性研究所の木下實教授(現・山口東京理科大学教授)によって発見されたp-NPNN(p-ニトロフェニルニトロニルニトロキシド)という有機化合物です(図2)。この有機化合物の結晶は0.6Kという極低温で、強磁性的な秩序状態に相転移して、磁石に吸着するようになります。不対電子を統一する交換相互作用は、有機ラジカル分子間ではきわめて小さく、熱振動によってスピンの向きはバラバラとなっています。しかし、温度を下げると不対電子間の交換相互作用が起き強磁性体となるのです。
現在、実用的な有機磁石の開発に向けて、さまざまなアプローチから精力的に研究が続けられています。もし常温でも強磁性を示す有機磁石が発見されれば医療にも利用できるようになるといわれます。薬と結合した有機磁石を体内に投与すれば、外部磁界によって患部に効率的に運ぶことが可能になるからです。
生命機能も広い意味での化学反応であり、そこには電子の振る舞いが深く関与しています。21世紀は、有機磁石をはじめとする機能性高分子の発達が、エレクトロニクスとバイオテクノロジーとをドッキングさせる主役となるかもしれません。

TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです