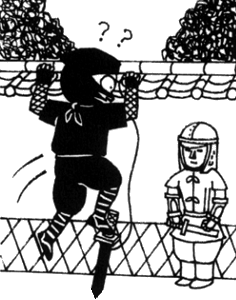じしゃく忍法帳
第55回「変わりだねの磁石」の巻

鉄なしでも磁石はできる
白金カイロは触媒反応の利用
茶席で出される料理のことを懐石料理といいます。もともと懐石というのは、寒さをしのぐため、禅僧などが熱した石(温石=おんじゃく)を布でくるみ、これを懐に入れたことに由来します。懐石料理とは腹を温めるほどの軽い料理という意味。豪華料理を期待してはいけません。
温石は重いうえにすぐに冷めてしまうので、忍者は“胴の火(図1)”というカイロ(懐炉)を携帯しました。これは銅製の筒に和紙や植物繊維を黒焼きにしたものを詰めたもの。点火するとゆっくりと燃えて半日ほどもつので、懐に入れて暖をとるだけでなく、火種としても利用しました。
今日まで伝えられる忍法書の多くは、江戸時代初期に著されています。天下泰平の徳川の時世になると、忍者の活躍の場が少なくなり、秘伝の忍法を後世に残すため、忍法書が書かれたようです。胴の火は『正忍記』という紀州流忍法の秘伝書に載っています。『正忍記』が著されたのは延宝9年(1681年)、一方、カイロの発明は元禄年間(1688〜1704年)といわれているので、おそらくカイロは忍者の胴の火が民間に転用されたのでしょう。
胴の火方式のカイロは昭和初頭まで長らく使われましたが、その後、ハッキンカイロという新タイプが登場しました。これはベンジンを燃料とし、白金(プラチナ)の細線を触媒としたもの。白金表面でベンジンが徐々に酸化されるとき発生する熱を利用します。触媒反応という近代化学の成果を生かしたカイロでしたが、白金は高価なうえ、ベンジンには引火性もあるため、現在では安全な使い捨てカイロが使われるようになりました。
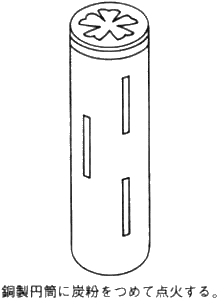
図1 胴の火(忍者が携帯したカイロ)
特殊用途で使われる超高価なプラチナ磁石
白金は周期表第8族に属する貴金属。金や銀は古代から知られていましたが、白金の発見は意外と新しく、18世紀に南米で銀に似た新金属として採掘されたことに始まります。
白金は金や銀と同じく展性・延性に富み、また他の多くの金属とも容易に合金をつくります。磁石に吸いつきませんが、面白いことに白金・鉄・ニオブ系の合金は磁石材料となります。これをプラチナ磁石と呼んでいます。
プラチナ磁石に含まれる白金は重量で約70%、貴金属としての価値も十分にもつ超高価な磁石です。趣味的に製造された磁石のように思えますが、磁気性能はアルニコ磁石よりもすぐれ、金属磁石の中では最強の磁気パワーを誇ります。しかもプラチナ磁石は鋳造磁石であるため、精密加工が容易なうえ、貴金属ならではの耐食性を有します。一般にはなじみが薄いものの、希土類磁石が登場するまで、高級時計や高級ステレオのカートリッジ用、医療用具などで使われていた磁石です。
磁石と鉄は親子のような間柄です。鉄が磁石に吸いつくのは、磁界によって鉄が磁石としての潜在的性質に目覚めるからです。鉄とともに強磁性元素であるコバルト、ニッケルも磁石に吸着します。プラチナ磁石にもわずかながら鉄が含まれますが、こうした強磁性元素をまったく含まない磁石も存在します。たとえばマンガン・アルミ磁石は、マンガンとアルミニウムと炭素という非磁性元素からなる磁石です。強磁性元素を含まないのに、磁石となるのは、いったいなぜでしょう?
強磁性のルーツは不対電子のスピン
物質の磁性は主に電子のスピン磁気モーメント(図2)に由来します。荷電粒子である電子が自転(スピン)すると、自転軸の方向に磁界が生まれるからです。しかし、どのような元素も磁石になりうるというわけではありません。たとえばヘリウムやネオンなどは、軌道上の電子のスピンが互いに反対向きとなって磁気モーメントを相殺しあい、マクロの磁性も示しません。しかも、軌道上の電子の指定席は満杯状態となった閉殻構造となっているので、化学的にも不活性で導電性も示しません。
一方、強磁性元素の原子構造は不完全殻となっていて電子が孤立して存在します。この不対電子(磁性電子)が、磁性の担い手になり、マクロの磁性を示すのです。
鉄原子には4個、コバルト原子には3個、ニッケル原子には2個の不対電子が存在します。しかし、これらの原子が強磁性体となるには、さらに次のような条件が必要です。
強磁性は交換相互作用と呼ばれる原子間の量子力学的な協力作用によって発現します。交換相互作用が働くには、まず原子が秩序をもった配列をしていることと、不対電子がころあいの距離を保っていることが必要です。金属結晶はこの条件を満たしますが、これだけでは十分ではなく、交換相互作用が維持できるような安定した磁気構造が結晶に存在することも必要です。永久磁石を熱すると、ある温度(キュリー温度)以上で、磁石としての性質を失い、常磁性体となってしまうのも、結晶の磁気構造が崩れてしまうからです。
これを逆にいえば、交換相互作用が働くような磁気構造をもつ結晶は、強磁性元素を含まない合金でも、磁石材料としての条件を満たすことになります。
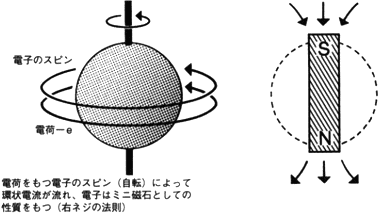
図2 電子のスピン磁気モーメントの発生原理
未知の可能性を残す合金や金属間化合物
合金とは2種以上の金属が入り混じった状態の物質で、この入り混じり具合は均一とはかぎらず、さまざまな金属組織や金属相の生成によって、機械的強度や電磁気特性などが微妙に変化するようになります。
マンガンもアルミニウムも非磁性元素です。しかし、これらの合金をつくるとき、時効処理と呼ばれる熱処理をほどこすと、異なる金属相からなる規則格子が分離・生成され、準安定状態ながら、強磁性を示すようになるのです。これはホイスラー合金と呼ばれ、以前から知られていましたが、1977年にマンガン、アルミニウムに炭素を加えると、強磁性相が安定化し、また保磁力も増大することが発見されました。こうして開発されたのがマンガン・アルミ磁石です。マンガン・アルミ磁石は、資源供給の面で不安がないのが利点。また機械的強度や切削加工性にもすぐれているため、モータの回転子や工具などに利用されています。
変わりだねの磁石の中で、最も注目されているのは超電導マグネット(図3)です。永久磁石が発生する磁界の強さは、その材料の飽和磁化の値が上限となります。これは電磁石でも同様で、いかに大電流を流しても、磁心材料の飽和磁化の値を超えることはできません。
しかし、空心コイルにおいては、理論的に発生磁界の上限はなくなります。超電導マグネットというのは、電気抵抗のない空心の超電導コイルに大電流を流したときに発生する磁界を利用したもの。ただし臨界温度を超えると超電導状態が壊れてしまうため、液体ヘリウムなどでコイルを冷却する必要があります。
1986年に発見された高温超電導体は、ランタン・バリウム・銅・酸素からなる電子セラミックス。高温といっても液体ヘリウムの温度にくらべての話ですが、その後の研究により、液体窒素の温度(−196℃)でも超電導現象が起きる超電導体が、いくつも発見されました。実用的な室温超電導体が開発されれば、エネルギー革命が起こることはまちがいありません。
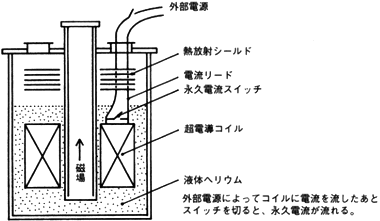
図3 超電導マグネットの構造
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです