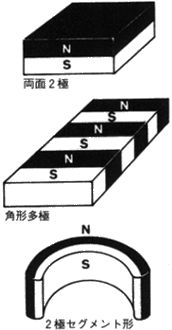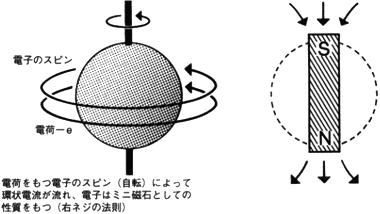じしゃく忍法帳
第53回「冷却技術と磁石」の巻

磁石でモノは冷やせるか?
平安貴族が賞味した夏の氷菓子とは?
忍法がマジックと似たところがあるのは、種や仕掛けがこっそりと隠されているからです。一方、種や仕掛けもないのに、常識では説明がつかない現象というのも自然界には数多く存在します。たとえば、昔から科学実験の出し物として演じられる“復氷”もそのひとつ。
氷の塊に糸の輪をかけ、糸に重りをぶら下げると、糸がしだいに氷に食い込み、やがて氷の塊をくぐりぬけてしまいます。糸の輪が通過したことで、氷の塊は真っ二つに切断されそうなものですが、意外にも元の状態を保ちます。もちろん、奇術の胴体切りのように、種や仕掛けが隠されているわけでもありません。
復氷と呼ばれるこの不思議な現象は、次のように説明されています。
糸が氷に食い込んでいくのは、重りが引っ張る圧力によって、氷の融点が下がるからです。このため糸の周辺の氷は融けますが、糸が通過して圧力が除かれると、融けていた水は再び凍結してしまうのです。2つの氷片を強く押しつけるとくっつくのも、加圧によって氷の融解と再凍結が起きるからです。
氷が実験室で人工的につくられはじめたのは18世紀以降です。それ以前は製氷機などなく、当然ながら夏季における氷は貴重品でした。
日本では律令時代に宮中ご用達の氷室(ひむろ)が各地に置かれ、毎年、旧暦の6月1日に、氷室に貯蔵しておいた天然氷を食べる行事がありました。これを“氷の朔日(ついたち)”といいます。清少納言は『枕草子』の中で、「削り氷にあまづら入れて、新しき金まりに入れたる」を「あて(貴)なるもの」として賞賛しています。あまづらとは天然の甘味料、金まりとは金属製のお椀のこと。現代風にいえば、かき氷の“みぞれ”のようなものですが、当時はめったに口にできない最高級の氷菓子だったのです。
冷蔵庫もエアコンも気化熱の応用
暑い盛りに庭や道路に水を撒くと涼しくなります。これは水が冷たいからではありません。水が蒸発するとき、大地の潜熱を気化熱(蒸発熱)として奪い去るからです。
エアコンや冷蔵庫などの一般的な冷却装置も、この気化熱を利用したものです。18世紀半ばに考案された初期の製氷機は、空気ポンプを用いて低圧で水を蒸発させ、そのとき奪われる気化熱によって低温状態をつくり、氷を製造するというものでした。しかし、これは実験的な装置にすぎず、実用的な製氷機とはなりませんでした。
19世紀になると、エーテルやアンモニアが冷媒(熱媒体)として使われるようになりました。エーテルやアンモニアはコンプレッサ(圧縮器)で加圧すれば容易に液体となり、圧力を取り去れば常温でも気化するのでつごうがよいのです。
使用中の冷蔵庫はときどきうなり音を出しますが、これは気化した冷媒を圧縮するコンプレッサのモータ音です。コンプレッサで圧縮すると発熱するので、この熱は冷蔵庫の背面に置かれたコンデンサ(凝縮器)から放熱され、高圧の冷媒ガスは液体となります。液体となった冷媒は、冷凍室のエバポレータ(蒸発器)に送られ、そこで気化するとき周囲から熱を奪い、製氷したり食品を冷凍・冷蔵します。これが冷蔵庫のしくみです(図1)。ちなみにエアコンはコンプレッサとコンデンサを室外に置いたもので、そのしくみは冷蔵庫と同じです。
冷媒にフロンを用いた冷蔵庫が登場したのは1930年代です。フロンは、化学的に安定で、冷媒に適していますが、大気中に放出されるとオゾン層を破壊することが判明しました。そこで、近年はオゾン層への影響が少ない代替フロン、プロパンやブタンなどの炭化水素が冷媒の冷蔵庫も開発されるようになりました。
しかし、冷却は必ずしも冷媒を必要としません。ある種の半導体を利用した電子冷却器は、すでに車載用冷蔵庫(あるいは温蔵庫)や簡易冷却器などに使われています。
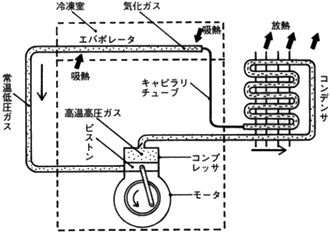
図1 冷蔵庫のしくみ
ペルチエ効果を応用した半導体方式の電子冷却器
電子冷却器は熱電半導体とかペルチエ素子などと呼ばれる半導体素子を利用したもの。最新の電子機器ですが、冷却原理そのものは100年以上も前に発見されていました。
1821年、ドイツのゼーベックは2種の金属の両端を接合して回路をつくり、接合部を異なる温度に保つと、回路に電流が流れることを発見しました(ゼーベック効果)。これを熱電流といい、回路を開くと生じる起電力は熱起電力といいます。
これとは逆の現象を研究したのは、フランスのペルチエです。1834年、彼は異なる金属を接合して電流を流すと、接点に熱の発生や吸収が起きることを発見しました(ペルチエ効果・図2)。ペルチエ効果はある種の半導体(ビスマス・テルル系など)でも起きるので、これを応用して開発されたのが電子冷却器です。冷媒も必要とせず、電子部品とも相性がいいので、パソコンのCPU(中央演算処理装置)の冷却用などにも使われるようになりました。
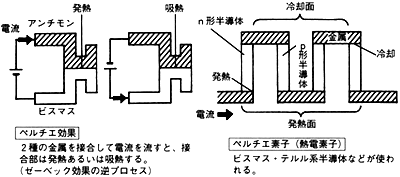
図2 ペルチエ効果とベルチエ素子の構造
極低温、超低温は断熱消磁で実現
ヘリウムは約4K(約−269℃)で液化して、液体ヘリウムとなります。約4K〜約0.01Kまでの温度範囲は、一般に極低温と呼ばれ、それ以下の温度は超低温と呼ばれます。超低温は通常の冷却装置ではつくりだせません。そこで利用されるのが、断熱消磁という物理現象です。
磁性体を構成する磁性原子の磁気モーメントの向きが、バラバラの状態であるとき、これを常磁性といいます。常磁性体に外部磁界を加えると、磁性原子の磁気モーメントは、磁界の方向に配列します。ここで外部磁界を取り去ると再び常磁性に戻りますが、このとき外部から熱を奪います。これを断熱消磁といい、0.001Kの超低温が 実現します。
さらに低い0.001K以下という超低温の実現には、核断熱消磁という手法が用いられます。
物質の磁性の大半は原子核の周囲を飛び回る電子のスピン(自転運動)と軌道運動によるものですが、一部は原子核も関与します。これは核磁気と呼ばれます。強力な磁界を用いれば、この核磁気モーメントの向きも揃えることができ、磁界を除去して元の状態に戻るとき、外部から熱を奪います。これが核断熱消磁です。絶対零度に迫る0.001K以下という超低温は、核断熱消磁という手法によって初めて実現できたのです。
核磁気は医療診断機器にも応用されています。MRI(磁気共鳴映像診断装置)は、体内の水素原子核の磁気モーメントを強い磁界によって、一定方向に揃え、それが元に戻るときに発せられる電磁波から体内情報を得る装置です。当初は大がかりな超電導磁石を必要としましたが、ネオジム磁石という強力な永久磁石の開発により、車載可能なほどの小型化が進みました。
物質のミクロの世界を解明するのに磁石は欠かせません。なぜなら、原子核も軌道電子も小さな磁石としての性質をもつからです。
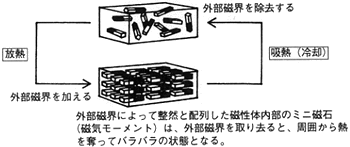
図3 磁気冷却の原理
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです