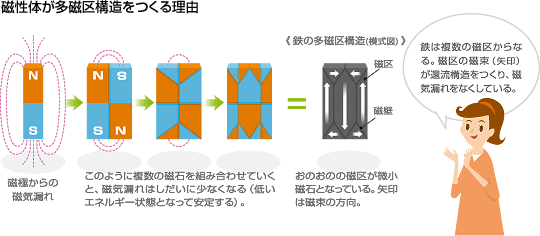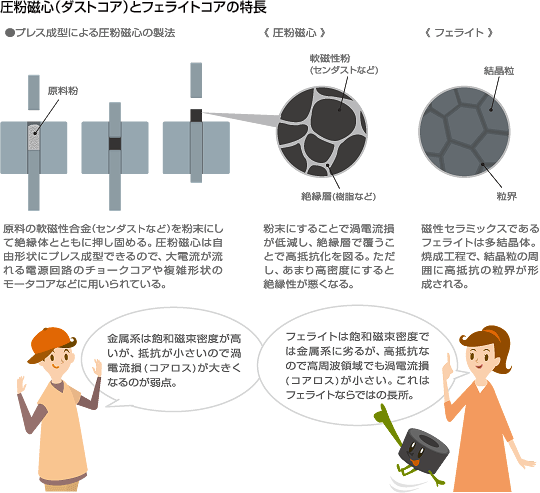フェライト・ワールド
第3回 アンテナコイルにフェライトコアが使われるのは?

天然磁石は地球が産んだフェライト磁石
磁石=マグネットの形容詞であるマグネチック(magnetic)という言葉には、“磁石の、磁気の”という意味のほかに、“人を引きつける・魅力的”という意味があります。琥珀(こはく)を摩擦するとチリや灰を引きつける現象(静電気)や、天然磁石(磁鉄鉱の仲間)が鉄を引きつける現象は、古くから知られていました。また、加熱するとチリや灰を吸い寄せるトルマリン(電気石)は、産地の名をとって“セイロン磁石”とも呼ばれました。モノを吸い寄せる性質は、昔はすべて人の心を引きつけてやまないマグネチックな存在だったのです。
鉱物学は19世紀の電磁気学、そして20世紀のエレクトロニクスの誕生にも大きく貢献しました。圧力を加えると電圧を発生する圧電現象は、電子ブザーや超音波振動子、圧力センサなどに利用されていますが、これはフランスのキュリー兄弟(兄:ジャック、弟:ピエール)により、トルマリンや水晶などの鉱物から最初に発見されました。
1930年、東京工業大学の加藤与五郎博士と武井武博士により発明されたフェライトもまた、閃亜鉛鉱など鉱石から亜鉛を取り出す工法の研究から誕生した電子材料です。亜鉛鉱石を焼いて酸化亜鉛としたのち硫酸で溶かし、これを電気分解すると亜鉛が得られますが、このとき鉱石に含まれる鉄酸化物が亜鉛と結合してフェライトとなります。亜鉛の収率を下げるやっかいな存在であったフェライトの研究をしているとき、偶然にも強い磁性を示すフェライトがあることが発見されたのです。こうして誕生したのが世界初のフェライト磁石であるOP磁石です。ほどなく両博士は軟磁性材料のフェライト(ソフトフェライト)も発明しました。その特許を譲り受けて工業化し、“オキサイドコア” という商品名で販売したのがTDKです(1935設立。当時の社名は東京電気化学工業)。
フェライトは2価の金属イオンM2+の酸化物(Mは元素記号ではなく、さまざまな金属元素を意味する略記号)と、3価の鉄イオンFe3+の酸化物が複合したMFe2O4 あるいはMO・Fe2O3の化学式で示される物質です。Mの位置にはコバルト、銅、マンガン、亜鉛など、さまざまな金属元素が入るため、きわめて多種多様なフェライトが得られます。 Mが鉄(Fe2+)の場合は、FeO・ Fe2O3 すなわちFe3O4となり、磁鉄鉱=マグネタイト(Fe3O4)の組成となります。紀元前の昔から人々を不思議がらせてきた天然磁石(磁鉄鉱の仲間)は、実は天然のフェライト磁石だったのです。自然のダイナミズムは地中に天然のフェライト磁石を産み、人類の技術は20世紀に人工のフェライト磁石をつくりだしたというわけです。
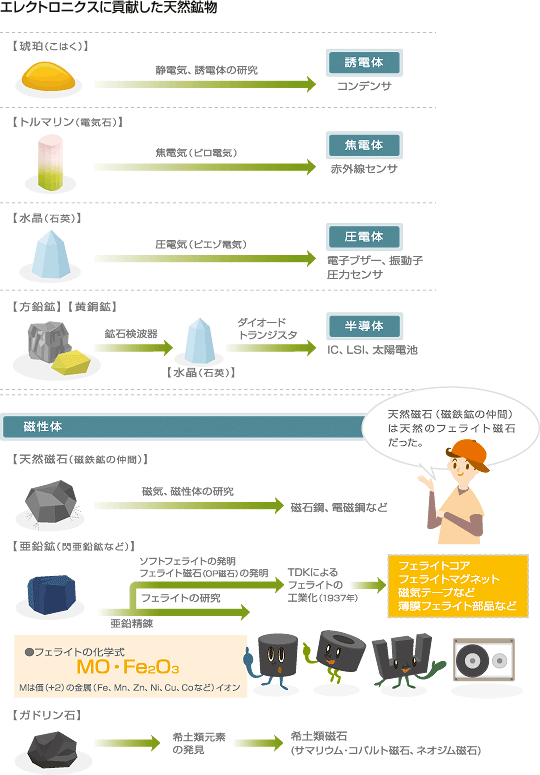
戦前ラジオのミュー(μ)同調器にも使われたTDKのフェライトコア
テレビのブラウン管などにも名を残すドイツの物理学者ブラウンは、1873年頃、後のダイオードやトランジスタ(点接触型)の発明の先駆ともいえる重要な発見をしています。黄銅鉱や方鉛鉱など、いろんな鉱物の電気抵抗を測定しているとき、プラスとマイナスの2つの電極の当て方によって異なる抵抗値を示すことに気づいたのです。これは単なる新現象の発見に終わりましたが、20世紀初頭に無線通信が始まると、電波をとらえるための鉱石検波器として利用されるようになりました。
初期の無線通信は、火花放電にともなって発生する電波を利用して、トンツー(短点・<トン>と長点−<ツー>で情報を信号化)のモールス信号を送るものでした。いわば電波のノロシのような無線通信です。技術的に難しいのは送信機より受信機のほうでした。アンテナで受けた電波は交流電流として回路に流れます。これをたとえば電流計の針の振れによって知ろうとしても、双方向に流れる交流では、電流計の針は振れません。そこで、交流電流から一方向のみの電流を取り出す何らかの整流装置が必要です。これを検波器といいます。
いろんなタイプの検波器が考案されましたが、しくみがシンプルなため多用されたのが鉱石検波器です。方鉛鉱や黄銅鉱といった天然鉱石の表面に電極の針を当てて、最も受信感度のよい場所を手探りで見つけます。これは一方向にのみ電流を流すダイオードと原理的に同じものです。
1920年代にラジオ放送が始まると、鉱石検波器はラジオ受信機にも使われました。いわゆる“鉱石ラジオ”です。ラジオ放送の受信には、送られてくる電波の周波数に同調(チューニング)させなければいけません。それにはコンデンサとコイルを組み合わせたLC同調回路が使われました。 LC同調回路には、コンデンサ(C)の容量を可変にするタイプと、コイル(L)のインダクタンス(コイルが発生する磁力線の量)を可変にするタイプがあります。下図に示すのは、フェライトコアを用いたミュー(μ)同調器。フェライトコアをコイルの中に入れることで多くの磁力線を集め、フェライトコアをコイルの中で動かすことでインダクタンスを変えて、放送電波の周波数に同調します。
1930年代は高周波技術の成長期。TDKのフェライトコアは、ラジオ受信機や無線通信機のアンテナコアなどとして、終戦(1945年)までに約500万個も製造されていました。TDK歴史館 (秋田県にかほ市)には、 ミュー同調器を用いた戦前のラジオなど、エレクトロニクスの発展史をたどるうえで貴重な多数の製品が展示されています。
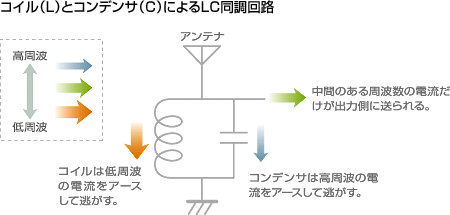
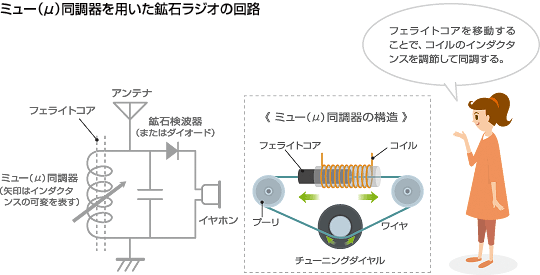
自動車のキーレスエントリーシステムでも活躍するフェライトコア
2つの棒磁石を磁極を反対向きに抱き合わせると、鉄を吸い寄せなくなります。これは磁力線が磁石内部を還流するようになり、磁極が外部に現れなくなるからです。フェライト磁石を粉砕すると、砕片のそれぞれが微小磁石となり、互いに吸いついて団子状になります。団子状になったフェライト磁石は、やはり鉄を吸い寄せなくなります。これもまた、多数の微小磁石がバラバラの向きで互いに吸いつきあっているためです。
鉄やフェライトなどの磁性体が磁石に吸いつく理由は、これをモデルとして考えるとわかりやすいでしょう。鉄やフェライトなどの磁性体は、多数の微小磁石からなりますが、通常は磁極の向きがバラバラです(磁力線の還流構造をつくっている)。このため鉄が鉄を吸い寄せたり、フェライトがフェライトを吸い寄せたりすることはありません。しかし、外部から磁界が加わると、バラバラだった微小磁石は磁界の方向に勢ぞろいします。すると全体で1つの磁石のようになり、外部の磁石と吸いつきあうのです。
磁性体に交流磁界が加わると、磁界の向きが切り替わるたびに、微小磁石の向きは反転します。この反転の立ち上がりやすさを透磁率といい、kHz、MHz…といった高周波領域では、きわめて重要な特性となります。たとえば自動車のキーレスエントリーは、キー側と自動車側で電波をやりとりして、キー挿入なしにドアを開閉したり、エンジンを始動したりするシステムです。キーにはトランスポンダコイルという小さなアンテナコイルが搭載されています。ここには低損失で高透磁率そして温度変化にも安定したフェライトコアが使われます。微弱な電波をとらえ、数年間もバッテリ交換なしに使用できるのも、小さくても高特性のフェライトコアが用いられているからです。
トランスポンダコイルは、自動車のイモビライザ(盗難防止システム)やタイヤ空気圧監視システムなどにも使われています。フェライトという材料は、電子機器の小型化や省エネのみならず、安全性、快適性、セキュリティ面でも、多彩な活躍をしています。
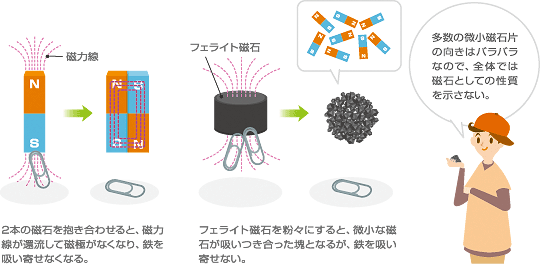
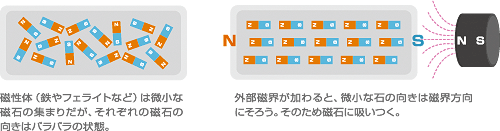
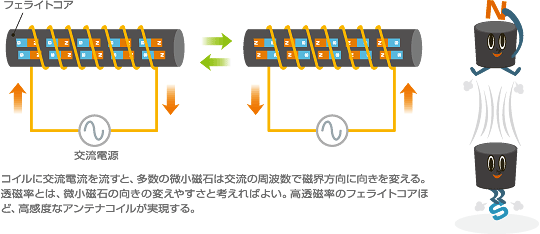
TDKは磁性技術で世界をリードする
総合電子部品メーカーです