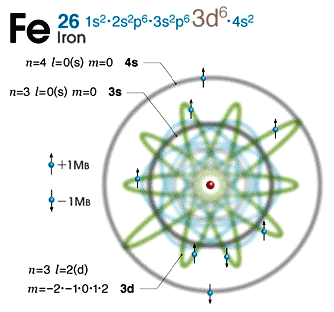With ferrite by TDK
GRAIN1 磁性の裏にひそむ極小磁石

序に代えて

ご承知のとおり、永久磁石に宿るNとSの2つの極は、たとえ粉薬のような微粉末になるまで磁石をすりつぶしても消えてしまうことはない。そのような磁石の特性が一般常識とされている今日、初めて磁石を手にしたこどもが、N極、あるいはS極だけの粒子がノリで固められていると主張するのを笑うのは簡単である。だが、磁気と表裏一体の関係にある電気の世界においては、自由電荷と呼ばれる+と-の電荷がそれぞれ単独に存在して当たり前なのだから、笑いにもついつい抑制が利いてしまう。そして、この不可解な気分は、どうやら個人的なものでもなさそうである。

私達の宇宙は、いまから約百数十億年前に創成されたと推定されているが、その歴史の初期に、磁気単極子(magnetic mono-pole)が作られたという議論がある。実際にこれまで多くの研究者によってN極やS極だけの粒子を探し求める真剣な試みが続けられてきた。しかし、そうした努力にもかかわらず、確かな報告はいまだなされておらず、現在ではあくまで論理的な素子として磁気単極子を位置づける見方が主流となっている。しかし、そこまでしても見つからないのは最初から存在しないからだ、と決めつける必要も、またどこにもみあたらない。仮にそのような決めつけがまかりとおるものなら、メンデレーエフがその存在を予言したガリウムやスカンジウムなどの元素も、未確認の白抜き文字のままわびしい思いに泣かされ続けたことであろう。
そこで少々言葉を選ぶならば、現在広く受け入れられている量子論の知性は、磁石が宿す磁気的なエネルギーの最小単位を磁気単極子ではなく、N極とS極を同時に所有する最小の"磁石"、すなわち超ミクロな磁気モーメント(磁気双極子)に求め、永久磁石はもちろんのこと、本稿の主要なテーマとなっているソフトフェライトも含め、あらゆる物質に宿る磁性の秘密を、そうした極小磁気モーメントの相互作用の結果として解き明かそうとするのである。しかし、私達はいかなるイメージで、超ミクロな最小の"磁石"を思い描けばよいのだろうか。少なくとも、最小磁性単位というからには、それ以上には分割できない最小の物質に宿るものでなければならないはずである。
種明かしをすると、その物質とは、名前こそおなじみだが、いまだにその痕跡だけしか確認されていない極小粒子、電子そのものなのである。もちろん、ここで言うところの電子とは、19世紀後半にプランクにより導入され、数年後の20世紀初頭、アインシュタインによって革命的な展開を加えられた後(DETAIL)、まさに劇的ともいえる勢いで今日の物性論の根幹を占めるに至った"量子化された"電子である。しかし、私達はここでその歴史の詳細に立ち入ることはさし控えておこう。本稿の目的は、電子に宿る極小の"磁石"が、いかなる法則にもとづき、どのような機構をとおして巨視的なエネルギーにまとめあげられていくのか、そのミステリアスな極小宇宙のドラマをじっくりと堪能することにある。
そこで、次節では、神秘のベールに幾重にも包まれたフェライト極小宇宙に旅立つ前のかるい準備体操をかねて、原子核の正電荷にとらえられた電子の動きを追いながら、超ミクロな磁気モーメントにまつわるいくつかの基本的な約束事に触れておくことにしよう。
※DETAIL:19世紀末、イギリスの物理学者、レイリーとジーンズによって得られた熱放射の法則には、物質から放射される光のエネルギー(例えば、ガスの炎で鉄釘などを熱すると赤い光を発するように)は、波長が短くなればなるほど、つまり紫外領域に近づくほどに無限大となってしまうという矛盾を抱えていた。この問題に長い間取り組んでいたドイツの物理学者プランクは、1900年12月14日、ドイツ物理学会において、「波動のエネルギーは、任意かつ連続的に無限に小さく分割できる量ではなく、単独に存在する極めて小さなエネルギーの単位量(量子)の不連続な合成としてとらえるべきである」と発表した。しかし、マクスウエルの古典的電磁気論が支配的であった当時の物理学界の反応は冷たく、この量子概念の正当性を大胆にも全面的に評価し、いち早く物理学上の難題を解決する理論構築に導入したのは、それから5年後の1905年、光は波であると同時に粒子としての性質も合わせ持つとした「光量子仮説」で、一大センセーションをまきおこすことになる若きアインシュタインであった。
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです