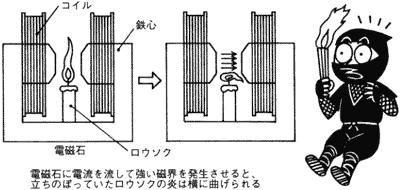じしゃく忍法帳
第65回「電波と磁石」の巻

無線通信で活躍した磁石
ボルタ電池による人類初の電気照明
相手のスキを見つけて一気に術を仕掛けるのが忍法の基本。目にも止まらぬ電光石火の忍者の早わざは、幻術・妖術とも呼ばれました。
もともと電光石火とは、はかない命をたとえた仏教語。電光は雷の稲光、石火は火打ち石の火花を意味します。雷が放電現象であることが実証されたのは18世紀のことですが、面白いことに古代中国において、すでに雷は「陰陽が出会って激しく光り輝く」現象と考えられていました。電気のプラス極・マイナス極が陽極・陰極と名づけられたのも、この中国の陰陽理論からくるものです。
摩擦電気(静電気)は紀元前の昔から知られていました。しかし、持続的な電気である電流が利用できるようになったのは、18世紀末に初の電池であるボルタ電堆(でんたい)およびボルタ電池が発明されてからのことです。
電流の利用はまず照明から始まりました。1815年、イギリスの化学者デービーは、2000個のボルタ電池をつないでアーク灯をともす大公開実験を行いました。
アーク灯とはアーク溶接と同じアーク放電による照明です。炭素棒の電極に適度の隙間をあけて電源につなぐと、アーク放電が始まって強烈な光が得られます。とはいえボルタ電池は短時間で放電してしまうため、実用的な照明の電源にはなりません。アーク灯が灯台その他の照明に使われるようになったのは、発電機が開発された1870年前後のことです。
さて、マクスウェルが電磁理論を確立し、光が電磁場の振動つまり電磁波の一種であることを数学的に説明したのもこのころです(1864年)。しかし、マクスウェルの方程式から必然的に導き出されるとはいえ、当時は電磁波の発生装置も、それをとらえる検出装置(検波器)もなく、電磁波は長らく仮説的な存在でした
放電火花はなぜ電磁波を発生するのか?
目に見えない電磁波の存在を実験的に明らかにしたのはヘルツです。他の多くの科学的発見と同様に、電磁波の発見にも偶然が幸いしていました。1888年、物理実験用に蓄電していたライデンびん(蓄電器の一種)の端子間に放電火花が発したとき、たまたま部屋の隅にあった別のライデンびんにも火花が発したのがヘルツの目に止まりました(図1)。何らかの力が空間を隔てて作用していると考えたヘルツは、これこそマクスウェルが予言した電磁波によるものと確信したのです。
放電火花が電磁波を生む現象は、簡単な実験で確かめられます。たとえば図2(上)のように、ヤスリと鉄クギを導線で電池と結び、鉄クギでヤスリをこすると、火花の発生とともに、ラジオにガリガリという音が発生します。また、電子ライターをラジオのそばで着火しても、ブツンというノイズが聞こえます。ただし、ライター石を使ったフリント式のライターでは影響は現れません。ノイズとなるのは放電に伴う火花なのです。では、放電火花はなぜ電磁波を発生させるのでしょうか?
放電火花は一方通行の放電ではなく、実は端子間で電荷が往復する電気的な振動現象です。端子間の電界は周期的に変化するため、その周囲にはリング状の磁界が発生し、磁界の変動はまたその周囲にリング状の電界を発生させます(電磁誘導の法則による)。こうして、電界と磁界が鎖のように交差して、次々と空間を伝わるのが電磁 波です(図2・下)。
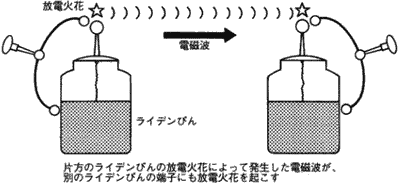
図1 電磁波の発見をもたらした現象
目に見えない電波をいかにしてとらえるか
ヘルツの実験が伝えられると、すぐに多くの学者・技術者が電磁波を遠距離通信に利用することを考えつきました。つまり電波による無線通信です(電波とは電気通信に用いられる電磁波のこと)。
ヘルツの実験装置はライデンびんを改良したような簡単な装置で、検波器としては狭い間隙をあけたループ状の導線が用いられました。しかし、これでは遠距離通信は困難なので、そこでまず開発目標となったのは感度のよい検波器です。
おりしも金属の導電性を研究していたフランスのブランリーは、ニッケル粉末には直流電流は流れないものの、なぜか高周波電流は流れるという現象を発見し、イギリスのロッジはこれを検波器として利用できることを思いつきました。こうして開発されたのがニッケル粉末をガラス管に詰めたコヒーラ検波器です(ブランリー管とも呼ばれました)。
コヒーラとは密着するという意味の英語です。バラバラのニッケル粉は到来した電波の作用によって、互いに密着して導電性を示すと考えられたことからのネーミングです。
コヒーラ検波器によって受信感度は格段によくなりましたが、問題はニッケル粉がいったん密着して導電状態になると、いつまでも電流が流れっぱなしになるということです。これでは持続的に電波を受信することができません。ただ、導電状態になったニッケル粉に衝撃を加えると、密着したニッケル粉がバラバラに離れて元の状態に戻ります。そこでコヒーラを導電状態から元の半絶縁状態に戻す機構=デコヒーラ機構が考案されました。
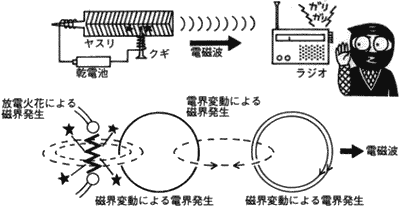
図2 放電火花による電磁波発生のしくみ
初期の無線通信機には電磁石式デコヒーラが利用
電磁リレーと同じ原理の力学的機構のデコヒーラを考えたのはロッジで、ロシアのポポフとイタリアのマルコーニは、このデコヒーラを搭載した実用的な無線通信機を発明しました。
図3に示すのは、1894年、ポポフが発明した無線通信機の受信機の回路図です。アンテナが電波を受信すると、コヒーラ検波器が導電状態となり、電磁石(A)が作動します。すると電磁石に吸い寄せられた鉄片が接点を閉じ、もう一つの電磁石(B)も作動し、ハンマーがベルを叩くとと同時に、接点が離れてバネの力で引き戻され、コヒーラ検波器を叩きます(デコヒーラ機構)。この衝撃によって密着したニッケル粉はバラバラになるので、導電状態から元の半絶縁状態に戻るという仕掛けです。
ところで、初期の無線通信に使われた電波は、今日でいえば電磁ノイズです。この種の電磁ノイズは広い周波数帯域をもっているため、混信という問題が避けられません。無線通信を実用化するためには、特定の周波数の電波を効率よく送受信できる装置が必要となります。そこで、同調回路が考案され、マルコーニはこれをいちはやく採用して、1901年、大西洋横断無線通信実験に初成功をおさめました。
マルコーニは磁気検波器という磁石を利用した検波器も発明しました。これは鋼線式の磁気録音機(テープレコーダの前身)にも似た面白い装置です。鋼線を磁石で磁化しながらエンドレスで回転させる機構で、磁化した鋼線はアンテナと結んだコイルの内部を通過するようになっています。アンテナが電波をキャッチすると、コイルに電流が流れますが、そのとき発生する磁界によって鋼線の磁化が変化します。この磁化の変化を別のコイルで電流として取り出し、信号を再生する仕組みです。磁気検波器は感度にすぐれ、また通信速度の向上ももたらしたため、鉱石検波器が普及するまで、船舶通信などに広く使われました。
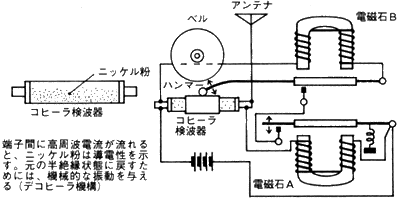
図3 ポポフの無線通信機の受信回路
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです