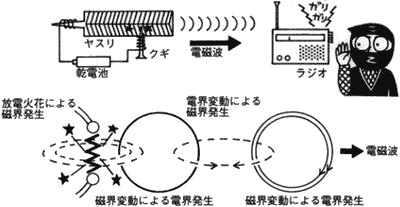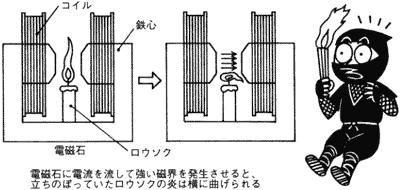じしゃく忍法帳
第64回「ミニ磁石の観察法」の巻

磁石に最小単位はあるか?
フォルムに現れる造化(自然)の妙
追っ手から逃れるために忍者が使う道具として鉄ビシがあります。4本のトゲのある立体鋲(びょう)のようなもので、これを地面や床に撒くと、トゲの1本は必ず上を向くので、追っ手が踏みつけると足の裏を貫きます。簡単な道具ですが、かなりの威力を発揮したと思われます。
鉄ビシは天然のヒシ(菱)の実を真似たもの。ヒシの実はゆがんだ正4面体のような形をしていて、頂点はとがっています。忍者はヒシの実も利用しましたが、より効果を高めるために鉄ビシをつくったのです。
防波堤の波消しブロックに使われるテトラポットも鉄ビシと同じ形をしています(テトラは4の意味)。テトラポットの4つの頂点を結ぶと正4面体となり、牛乳のテトラパックなどにも採用されているのは、この構造が紙製でもつぶれにくく、また、すきまなく効率的に積み重ねられて、運搬にも便利だからです。
方解石の結晶はマッチ箱をひしゃげたような菱面体(りょうめんたい)、天然磁石(磁鉄鉱)の結晶は、ピラミッドを2つ合わせたような八面体です。自然界は美しい造形に満ちあふれています。幾何学は人間が頭でひねり出したものではなく、自然界にそのお手本があるようです。
磁石は割っても割っても小さな磁石となります。では磁石に最小単位というものがあるのでしょうか? あるとしたら、それはどのような形態をしているのでしょうか?
磁区は目に見える最小単位の磁石
いかなる物質も原子や分子からなります。磁石も細かく砕いていけば、いつか必ず限界に達するはずです。そこで、19世紀末ごろに分子磁石というものが仮想されました。また、20世紀になると物質の磁性のルーツは、原子の磁気モーメント(主に電子のスピン磁気モーメント)にあることが解明され、これは原子磁石(あるいは電子磁石)と呼ばれるようになりました。とはいえ、仮想的存在である分子磁石はもちろん、原子磁石や電子磁石は、どれほど高倍率の電子顕微鏡でも確認することはできません。磁石の最小単位は物理モデルとして考えられるだけだったのです。
ところが、マクロレベルでの磁石の最小単位が、わずか100倍程度の光学顕微鏡で観察できることが、1930年代に明らかにされました。これは磁区(magnetic domain)と呼ばれます。
磁区という概念を提唱したのは、20世紀初めのフランスのワイスで、強磁性体の謎解きの突破口となる卓見でした。
強磁性体とは磁石に吸着する物質のことです。鉄は代表的な強磁性体であり、磁化されて磁石にもなります。19世紀から20世紀の初めにかけて、学者たちを混乱させたのは、鉄(強磁性体)と磁石との関係です。簡単にいえば「磁石はなぜ鉄を吸いつけるのか?」「鉄はなぜ磁化して磁石となるのか?」「なぜ鉄は鉄を吸いつけないのか?」といった問題です。磁石を分子磁石の集合体とするような単純なモデルでは、こうした現象を説明できないのです。
20世紀の磁区の発見(正確には磁区構造の発見)は、紀元前の天然磁石の発見に匹敵するほどの大発見です。磁区の存在の確認によって、強磁性体の磁化過程も詳しく理解できるようになったからです。
磁区を観察する方法はいろいろありますが、最も簡便なのは磁性流体(第6回「不思議な磁性流体」で詳述)を用いる方法です(図1左)。磁性流体とは強磁性体の微粒子を溶液中に分散した磁性コロイドです。これを強磁性体(鉄など)の試料の表面に滴下して顕微鏡でのぞくと、さまざまな幾何学的模様として観察できます(図1右)
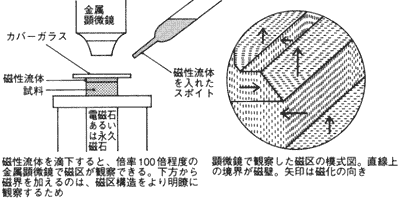
図1 磁性流体を用いた磁区の観察法
磁区は磁極を隠すように互い違いに寄り添う
磁区とは原子のスピン磁気モーメントの方向が揃った小領域で、通常の強磁性体は、複数の磁区が寄り添った多磁区構造となっています(図2左)。このような構造をとるのには理由があります。
磁区というミニ磁石を通常の磁石に置き換えて考えてみます。たとえばフェライト磁石はセラミックスなので、ハンマーで叩けば簡単に割れて不定形なカケラとなり、このカケラの1つひとつが磁石としての性質を保持します。しかし、さらに細かく砕くと異極どうしが吸着し合った1つの塊となり、全体として磁石の性質を示さなくなります。
それと同様に、強磁性体においてはミニ磁石である磁区が、磁化の方向を互い違いにして寄り添っているため、全体として磁石の性質を示さなくなります。棒磁石を保存するとき、磁極を互い違いにして抱き合わせるのも同じ理由によるものです。そのほうがエネルギー的に安定な状態となるからです。強磁性体とはいわば磁石となる資格をもつ物質ですが、ふだんはつつしみ深くその資格を隠しているのです。
顕微鏡で観察される磁区の図形は四角形や五角形の板を並べてさまざまな図形をつくるタングラム(知恵の板)を思わせます。もっとも、磁区というのは立体構造なので、むしろ木片を組み合わせた箱根細工に似ているといえます。箱根細工では木目を生かすために、木口(木材の断面)を隠すように組み合わされます。磁区においては木口にあたる部分が磁極です。磁極はなるべく露出しないほうが、エネルギー的に安定となるので、強磁性体は磁区の木口を隠すような還流磁区構造をとるのです。
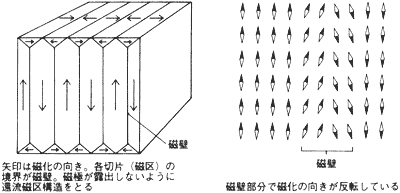
図2 還流磁区構造と磁壁
磁区の存在はまず音から確認された
箱根細工では木片は接着剤でつながれます。では、多磁区構造の磁区と磁区の境界はどうなっているのでしょうか? これは磁壁と呼ばれますが、壁という名がついていても、そこに物質的な仕切りのようなものはありません。磁壁とはある磁区の磁化の向きが反転する領域のことです(図2右)。このため外部磁界が加わると磁壁はスルスルと移動します。これを磁壁移動といいます。
このようすを図3に示します。強磁性体である鉄に磁石を近づけると、磁壁移動が起きて多磁区構造は、しだいに単磁区構造へと移り、全体が一つの磁石となって、近づけた磁石に吸着します。これが鉄の磁化過程であり、磁石が鉄を吸いつける理由です(鉄は自ら磁石と化すことで、磁石に吸いつきます)。
ただ、磁化過程とは複数の磁区が押し合い、へしあいする過程なので、磁壁移動は滑らかには進行しません。このため、鉄などの強磁性体を磁化すると、その初磁化過程のカーブは、微視的にはギザギザとしたものになります。
このギザギザは音として取り出すことができます。コイルを巻いた強磁性体に磁石を近づけると、磁化に伴ってコイルに微弱な電流が流れるので、それを増幅するとザーという雑音となって聞こえるのです。これは1919年に発見された物理現象でバルクハウゼンノイズと呼ばれます。実は磁区の存在が疑いないものと考えられるようになったのは、このバルクハウゼンノイズの実験がきっかけでした。磁区の存在は顕微鏡観察の前に、まず耳で確認されたのです。
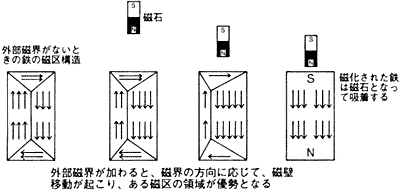
図3 鉄の磁化過程と磁区構造の変化
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです