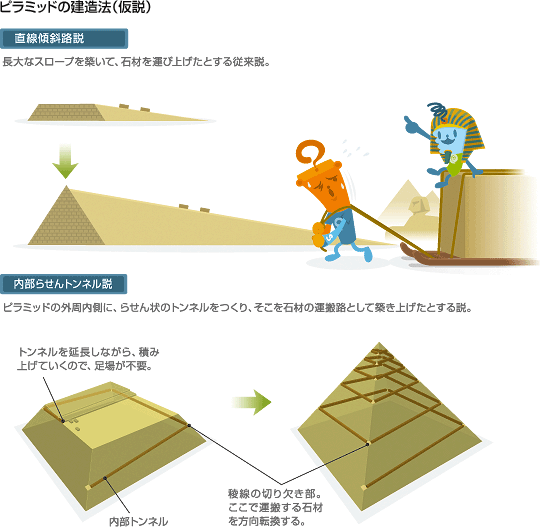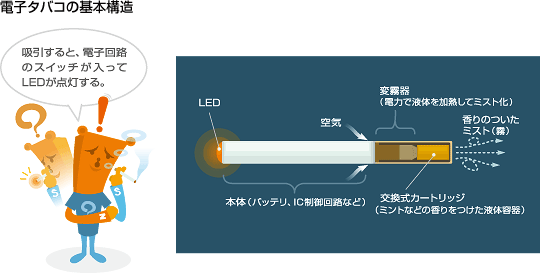電気と磁気の?館
No.42 カメラのストロボ発光とコンデンサの役割

舞台照明に使われた“石灰光”とは?
『ライムライト(limelight)』といえば、チャップリンが監督して自らも出演した映画(1952年製作)として知られています。もともとライムライトとは、まだ電球がなかった19世紀前半から20世紀初め頃まで、舞台照明などに使われた装置のこと。ここから「脚光」「名声」を意味する言葉にもなりました。
ライムとは石灰(酸化カルシウム)のことで、ライムライトは直訳すれば“石灰光”です。といっても石灰が燃えたりするわけではありません。物質を加熱していくと、温度に応じたスペクトルの光を放つようになります。これは黒体放射と呼ばれます。石灰は酸素と水素を混ぜて燃焼させた高温の酸水素炎(約2400〜2700℃)で熱すると、黒体放射により、まばゆい光を放ち始めるので、これを照明に利用していたのです。
ライムライトは過去のものとなりましたが、似たものはキャンプの燈火などに用いるランタンのマントルとして生き残っています。マントルとは合成繊維のネットにトリウムなどの物質を浸み込ませたもの。灯油やガソリンを噴霧して燃焼させ、その炎でマントルを熱すると、合成繊維のネットはトリウムを含む灰になり、その黒体放射により明るく輝きだします。
外部の炎ではなく、電流を流したときのジュール熱でフィラメントを輝かせるのが電球(白熱電球)です。明るく実用的な電球をつくるには、高温に耐えるフィラメントが必要になります。エジソン電球では、京都産の竹の繊維を炭化させた炭素フィラメントが用いられました。温度が2000℃にもなると、銅や鉄といった通常の金属は溶けてしまいますが、炭素の融点は約3500℃と高いので、短寿命ながら何とか輝き続けるのです。20世紀になると炭素並みの高融点金属であるタングステンを線材に加工する技術が確立され、タングステンフィラメントの電球が開発されました。
白熱電球では消費される電力のうち、光に変化されるのは数%にすぎず、残りは赤外線や伝導熱となってしまいます。社会全体で照明に要する電力は膨大です。そこで、省エネのために電球型の蛍光ランプに変えたり、近年はより効率的なLED(発光ダイオード)電球も利用されるようになっています。
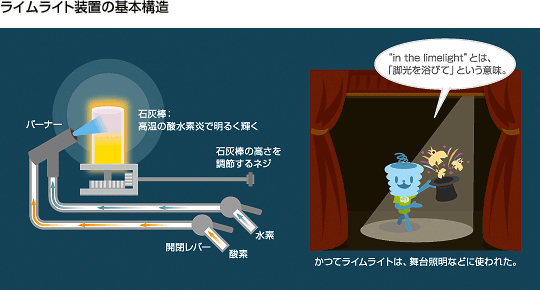
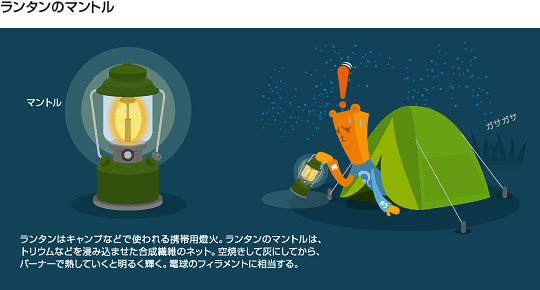
カメラのフラッシュは、なぜ“炊く”というのか?
初期の映画の映写機では、白熱電球が光源として使われましたが、大勢の観客を収容する広い映画館では、十分な光量が得られません。そこで、ライムライトが光源として利用されるようになりました。しかし、ライムライトは高温の酸水素炎を用いる装置であり、しばしば火災事故などが発生しました。このため1940年代には、発明まもないキセノンランプが使われるようになり、現在に至っています。
キセノンランプは希ガス元素であるキセノンを封入した放電管の1種。両端の電極(陰極と陽極)に高電圧を加えると、陰極から電子が飛び出して、陽極に向かって勢いよく加速されていきます。その途中で電子がキセノン原子に衝突すると、キセノン原子は高いエネルギー状態に励起され、元のエネルギー状態に戻るときに光を放出します。赤色に発光するネオン管とちがって、キセノンでは太陽光(白色)に近い光(連続スペクトル)が得られるのが特徴。このため、映写機ばかりでなく、プロジェクタの光源ほか、カメラのストロボにも利用されています。
ところで、フラッシュは“閃光”という意味ですが、カメラではフラッシュを“炊く”と表現するのはなぜでしょう? これは昔の写真撮影では、マグネシウムの粉末を燃焼させて(炊いて)、閃光を得ていたことによります。マグネシウムは酸化しやすい金属で、粉末にすると容易に燃えるのです。しかし、火薬を扱うようなものなので事故も起きやすく、細心の注意と熟練を要しました。これを簡便化したのがフラッシュバルブです。酸素を封入した小電球で、電流を流すとフィラメント(マグネシウムやアルミニウム)が一瞬のうちに燃え尽きて閃光を放ちます。ただ、一回切りの使い捨て電球なので、かつて報道カメラマンは多数のフラッシュバルブをバッグに入れて取材にあたりました。
フラッシュバルブと違って、繰り返し発光できるのがストロボの便利なところ。小型のキセノンランプを用いた電気的な発光装置(エレクトロニックフラッシュ)で、燃焼の閃光を利用するわけではありませんが、昔からの伝統でストロボもまた“炊く”と言ったりします。
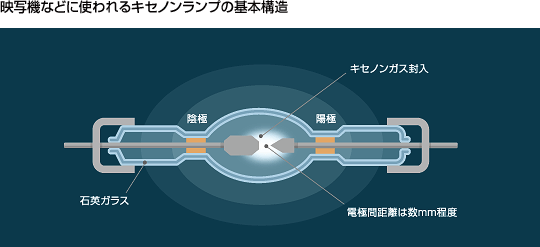
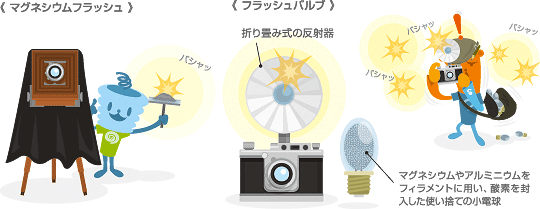
ストロボ発光を実現する電子回路とコンデンサ
ストロボのキセノンランプ(キセノンフラッシュランプ)は小さいとはいえ、発光には数千Vもの高い電圧が必要です。しかし、内蔵バッテリの電圧はわずか数V。これを数千Vの電圧にまで高めるために、専用の電子回路が搭載されています。
交流の電圧変換にはトランス(変圧器)が利用されますが、バッテリ電流は直流なので、そのままでは電圧変換できません。そこで、直流を制御ICなどによってパルス状の電流(1種の交流)に変え、パルストランスで数百Vの直流に変換します。これは簡易な昇圧型のDC-DCコンバータです。
数百Vに高められた直流は、大容量の電解コンデンサを充電し、満を持して待機します。ストロボ用のキセノンランプは、両端の電極のほか、管の外側にトリガ電極という電極をもっています。トリガとは“引き金”という意味です。このトリガ回路にも、小さなトリガトランスとトリガコンデンサと呼ばれるコンデンサが使われます。シャッターボタンを押すと、それと同調して、このトリガコンデンサに蓄えられていた電荷が放出され、トリガトランスによって数千ボルトにまで昇圧してトリガ電極に送られます。すると、この高い電圧によってキセノン管のキセノンはイオン化し、キセノンランプ内部は導電状態となり、大容量コンデンサに蓄えられていた電荷がいっきに流れ込んで、ストロボが発光するというしくみです。つまり、トリガ電圧によって絶縁体であるキセノンガスに絶縁破壊が起きて点灯するわけです。このトリガコンデンサには高い電圧にも耐える特性とともに、回路の小型化も求められます。このため、高耐圧タイプの積層セラミックチップコンデンサが使われます。
使いきりカメラに内蔵されているストロボも、同じしくみによるものですが、デジタルカメラでは受光センサによって、ストロボの発光量を自動調節します。電気的な発光装置であるため、ストロボはデジタルカメラとすこぶる相性がよいわけです。携帯電話では回路基板の省スペース化を図るため、搭載カメラのフラッシュには白色LEDが使われてきました。しかし、デジタルカメラ並みの高機能を実現するため、近年、キセノンランプによるストロボを内蔵したタイプも登場しています。
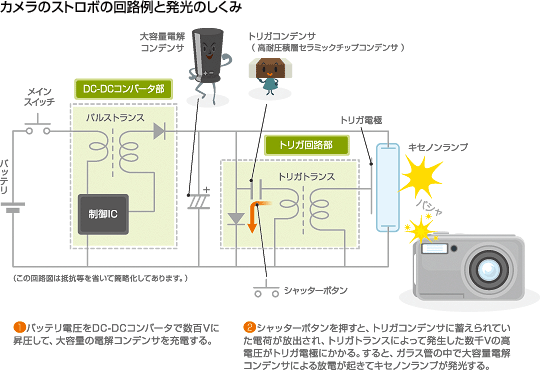
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです