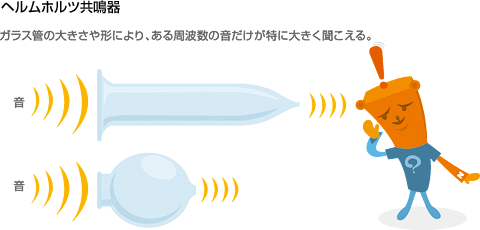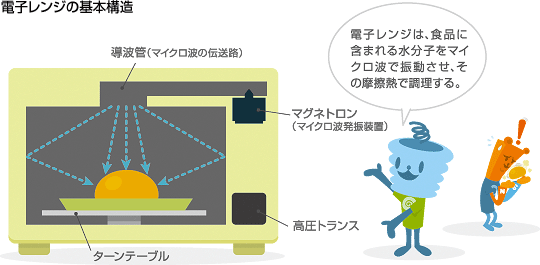電気と磁気の?館
No.30 テレビの歴史とテレビ技術の進化

世界初のテレビ放送は1935年にドイツで開始され、2011年に日本のテレビはすべてデジタル放送に切り替わりました。テレビ放送の実現や進化には日本の技術も大きく貢献しています。日本のテレビ放送の歴史と、この1世紀あまりにわたるテレビ技術の進化を振り返ってみました。
日本のテレビ放送の歴史
日本ではNHKが1953年2月1日に初めてテレビ放送を開始しました。同年の8月28日に日本テレビが民間放送初のテレビ放送を始めた後、日本全国でテレビ局が続々と設立されました。ただし、この頃のテレビはサラリーマンの平均所得の数十倍もする高額商品だったため、一般家庭で買うことは難しく、都市部に設置された街頭テレビの周りに人々が集まり、賑わいました。
1950年代後半から日本経済は高度成長期に入り、テレビは一般家庭に急速に普及。1959年4月10日、当時の皇太子殿下ご成婚の実況中継直前にはテレビの受信契約が200万台を超えました。1960年代以降、NHKと民放4局がカラーテレビの本放送をスタートしたことでカラーテレビが発売され、1964年の東京オリンピック開催を機にカラーテレビが広く普及。テレビ放送開始から22年が経過した1975年にはカラーテレビの世帯普及率が90%を上回りました。
以降、1980年代から衛星放送が始まり、1990年代からハイビジョン放送、2003年から地上デジタル放送が始まりました。そして2011年、日本のテレビはすべてデジタル放送に切り替わりました。
その後、2014年から4Kスーパーハイビジョン、2016年から8Kスーパーハイビジョンが試験放送を開始しました。高画質の4Kや8Kへの対応や、さらに美しい映像を映し出せるように、テレビは絶えず進化を続けています。
時計技術者のアイデアがファクシミリとテレビを生んだ
インターネットを利用した動画共有サービス“YouTube(ユーチューブ)”が人気を得ています。“Tube”とはアメリカにおけるテレビの俗称で、受像機のブラウン管(ブラウン・チューブ)に由来します。ちなみにブログなどで使われる“ようつべ”は、 “YouTube”をローマ字読みした隠語です。
ブラウン管はドイツの物理学者ブラウンによって考案された物理実験用の陰極線管(CRT)です。陰極線(真空放電において陰極から放出される高速の電子の流れ)の方向を制御して観察する装置で、これを受像機として応用したのがブラウン管テレビです。
世界初のブラウン管テレビの実験に成功したのは日本人技術者。浜松高等工業学校(現・静岡大学工学部)の高柳健次郎でした(1926年)。1940年の東京オリンピック(日中戦争の激化により開催中止)に向けて、国産技術によるテレビ放送も予定されていました。戦前の日本のテレビ技術は世界の先端をいくものだったのです(1941年に実験放送が開始されたが第2次世界大戦の勃発により短期間で中止)。
テレビはさまざまな技術成果の積み重ねによって完成されたもので、特定の発明者はいません。画像を電気的に伝送するというアイデアが生まれたのは19世紀半ば。ベルによる電話の発明(1876年)より約30年も前の1842年、イギリスのベインによって考案された装置が、テレビのルーツといわれます。これは“テレグラフ”と名づけられた化学式の画像伝送装置でした(下図)。テレビにはほど遠いとはいえ、画像走査つまり画像を多数の線に分解し、それを電気信号として伝送するというアイデアを実現したことで画期的なものでした。
ベインは時計技術者で、テレグラフの画像走査のしくみには、振り子の運動が取り入れられています。振り子の先に接触針を取り付け、振り子の往復運動により接触針で画像を走査して伝送するというしくみです。
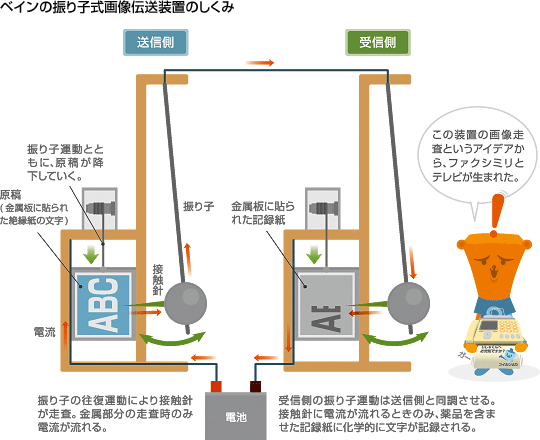
ブラウン管を採用したテレビは日本発の技術
ベインの装置はテレビというよりファクシミリの元祖と呼ぶべきものでした。実際、ベインの装置の改良から1920年代には実用的な写真電送装置が生まれ、のちに電話回線を利用するファクシミリが広く普及することになりました。
その一方で、ベインの装置は動画を電気信号で伝送するテレビの開発にも大きなヒントを与えました。19世紀末にはすでに映画の技術も誕生していましたが、映画とテレビは技術的にまったく異なるものです。映画のルーツはパラパラ漫画(本などの頁の片隅に人物などを描いて動画的効果を得る遊び)で、映画ではパラパラとめくるかわりに、写真フィルムをコマ送りして動画を得ています。映画は撮影も上映も光学的な器械で実現します。しかし、テレビは画像そのものを電気信号に変換して伝送し、それを画像として再生しようという新たなシステムです。
振り子の運動を利用したベインの装置では、静止画の伝送はできても動画は困難です。動画を伝送するには、画像の高速走査が必要だからです。そこでドイツのニポー(ニプコーとも表記される)は、小さな穴をらせん状にあけたニポー円板を考案しました(1884年)。円板の回転とともに、それぞれの穴が、被写体の画像を線状に切り取り、画像を分解するしくみです。
このニポー円板による機械式走査とブラウン管の受像機を組み合わせたのが、高柳健次郎が開発したテレビです。その仕組みを下図に示します。ニポー円板による走査線の光の強弱は、光電管(光センサとして機能する真空管)によって電気信号化されて受像側に送られ、筆で描いた「イ」の字がブラウン管にはっきりと映し出されました(1926年)。この装置はまだ有線式で、撮像も機械式であったとはいえ、受像側にブラウン管を用いたテレビとしては世界初のもので、完全電子式のテレビに大きく近づいた装置でした。
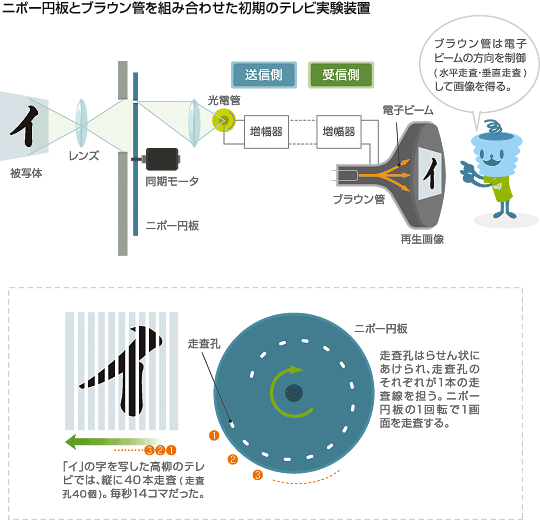
ブラウン管テレビでも活躍したフェライトコア
高柳健次郎は機械式走査による撮像では限界があることを早くから見抜き、これを電子走査する撮像管のアイデアを温めていました。撮像管というのはテレビカメラの心臓部で、電子式の撮像管なしにテレビ放送の実現もありえません。1933年にアメリカのツヴォルキンが初の撮像管であるアイコノスコープを開発しました。これは高柳が構想していた撮像管と同じ方式のもので、ほどなく高柳も国産アイコノスコープの開発に成功しました。
アイコノスコープやその改良型であるイメージオルシコンは光電子放出型と呼ばれるタイプで、室内での撮影には大掛かりな照明が必要でした。そこで、この問題を解決するために光導電型と呼ばれる高感度な撮像管が開発されました。固体撮像素子のCCDが利用されるまでテレビカメラに使用されていたビジコン、サチコンなどは光導電型の撮像管です。
第2次世界大戦により中断していた日本のテレビ技術は戦後まもなく再開され、1953年に本放送がスタートしました。この当時からTDKの電子部品はテレビ受像機に使用されています。なかでも重要部品として提供されていたのはブラウン管の偏向ヨークコアやフライバックトランスのコアといったフェライト製品。偏向ヨークコアはブラウン管の電子銃から放出された電子ビームを磁界で制御(水平走査・垂直走査)する偏向コイルのコア。フライバックトランスはブラウン管を駆動するために必要な高電圧をつくるための特殊なトランスです。
フェライトの工業化を目的に1935年に創業したTDKは、戦前にも約500万個のフェライト製品を生産し、無線通信機器やラジオなどに利用されていました。その技術は戦後の混乱期にも脈々と受け継がれ、テレビ時代にも生かされることになったのです。現在、テレビはブラウン管にかわって、液晶ディスプレイやプラズマディスプレイといったフラットテレビが主流となっていますが、フェライト製品をはじめとするTDKの電子部品は、フラットテレビの薄型化や省エネ化にも大きく貢献しています。
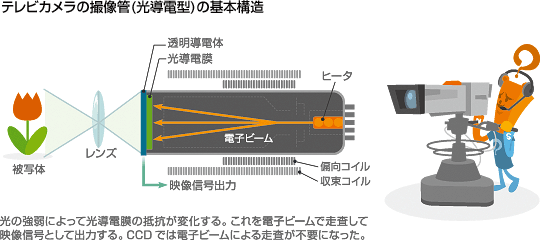
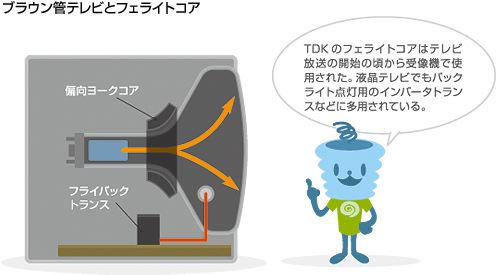
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです