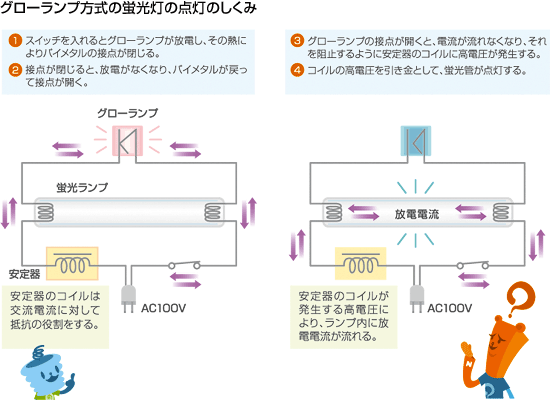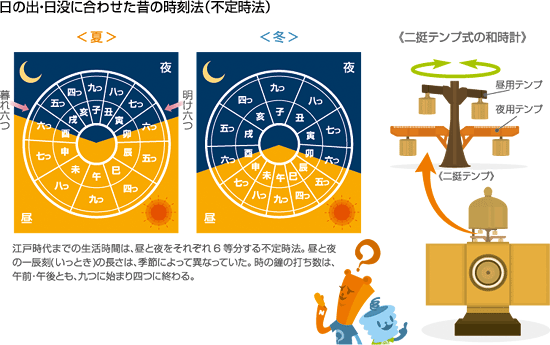電気と磁気の?館
No.13 エレクトロニクスを支える“めっき技術”

めっきは固体表面を金属の薄い皮膜でおおう技術。宝飾品や洋食器、金具、ネジクギなど、身の回りにはさまざまなめっき製品であふれています。奈良東大寺の大仏も、昔は金めっきでピカピカの仏像でした。めっきは古くて新しい技術。電子機器の小型化・高機能化にも、めっき技術は大きく貢献しています。
古代メソポタミアで電気めっき?
“めっき”は外来語のように思われていますが、実は“滅金(めっきん)”がなまったもの。金・銀などの貴金属の薄層を固体物質(金属や陶磁器その他)の表面にほどこす技術で、“鍍金(めっき)”とも表されます。奈良時代に、国中の銅を費やし、15年の歳月をかけて鋳造された東大寺の大仏は、仕上げに金めっきがほどこされました。水銀と金のアマルガム(軟らかい合金)をつくり、これを大仏表面に塗布したあと加熱すると、水銀が蒸発して金だけが残ってめっきされます。記録によれば約400kgの金と約2000kgの水銀が使われたそうです。
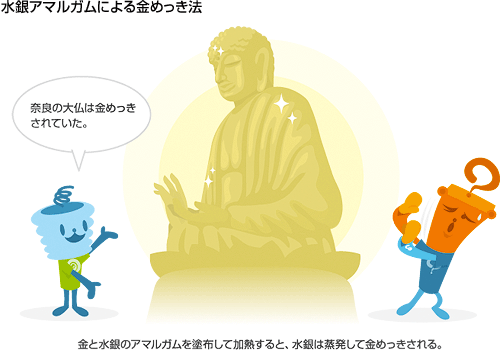
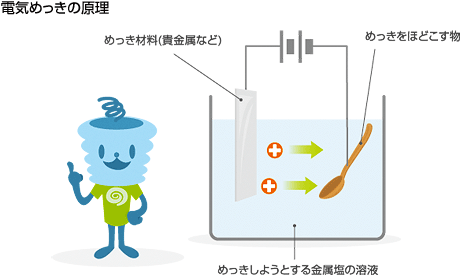
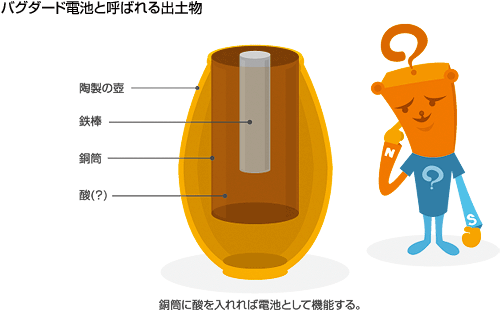
電池の発明により、19世紀になると宝飾品や洋食器などに電気めっきが利用されるようになりました。たとえばスプーンに銀めっきするには、スプーンと銀板を硝酸銀の溶液につけ、電池のマイナス極をスプーンに、プラス極を銀板につなぎます。こうすると硝酸銀溶液の銀イオン(陽イオン)は陰極のスプーンのほうに引かれ、表面に銀が析出してめっきがほどこされます。また、硝酸銀の銀イオンは、銀板から銀が溶け出すことで補給されていきます。
ところで、電気めっきは今から1500年以上も前のメソポタミアにおいて、実用化されていたという奇想天外な説があります。1930年代に、なんとも不思議な遺物が、メソポタミアの古代遺跡から出土していることが発表されたからです。これは高さ10cmあまりの素焼きの壺で、中には鉄棒をおさめた銅製のシリンダーが入っていました。鉄棒は酸で腐食した痕跡があるので、これはボルタ電池に先立つ古代の電池で、宝飾品の電気めっきに使われた可能性もあるという説が打ち出され、“古代電池”とか“バクダード電池”と名づけられたのです。はたして電気めっきに応用されたかは定かではありませんが、電池に似た装置で理科実験をおこなっていた古代メソポタミア人を想像してみるのも楽しいものです。
CD、DVDの金型は電鋳によって製造される
電気めっきは、かつての円盤レコードほか、CD-ROMやDVD-ROMを量産するときの金型の製造にも利用されています。この技術は電気鋳造を略して電鋳(でんちゅう。electroforming)と呼ばれます。
エジソンが発明した蓄音機は、回転する円筒ロウ管(当初はスズ箔を巻いた円筒)を録音媒体とするもので、音声振動を針に伝えてロウ管に溝を彫り付けていました。この方式では1度にせいぜい10本程度のロウ管にしか録音できませんでしたが、金型成型による円盤レコードでは大量生産が可能になり、世界的なレコード文化が生まれたのです。
円盤レコードの製造法はまずマスター盤の製作から始まります。音声の振動を電気的に増幅してカッターに伝え、ラッカーを塗った円盤レコードに溝を彫ってマスター盤(ラッカーマスター)をつくります。このマスター盤に電気めっきと同じ要領で金属めっきすると、マスター盤の凹凸とは逆の雌型ができます。この雌型を補強したものを金型とし、塩化ビニールなどの樹脂材料を成型したのが円盤レコードです。あたかもスタンプを押すように量産されるため、この金型はスタンパとも呼ばれます。
CD-ROMやDVD-ROMには、0か1かを表すピットと呼ばれる微細な凹凸が刻まれていますが、これらのディスクの量産にもやはり電鋳によるスタンパが使われます。CDのトラック幅は1.67ミクロン(µm)、DVDのトラック幅は0.74ミクロンしかありません。電気めっきと同じ原理で溶液中の金属イオンを移動させ、物体表面に金属を析出させていく電鋳は、ナノメートルオーダーの微細な凹凸も再現できるため、高精度の金型をつくることができるのです。
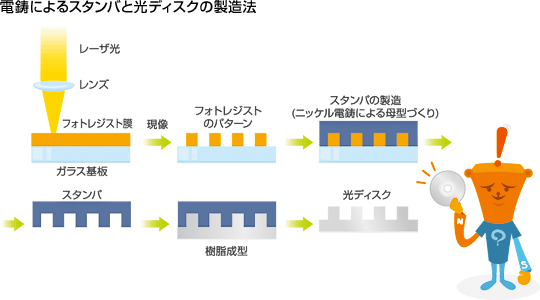
チップ部品の端子電極とめっき
携帯電話をはじめとする電子機器のリサイクルは、環境保全とともに貴重な資源を再利用する目的があります。電子部品には高価な金がめっき材料として多用されているためです。重量あたりの含有量は金鉱石よりも多いので、経済的にも十分にリサイクルする価値はあるのです。
主要電子部品の1つである積層セラミックチップコンデンサの内部電極材料としては、かつて貴金属であるパラジウムが多用されていました。積層セラミックチップコンデンサは、薄い内部電極と誘電体シートをサンドイッチ状に数100〜1000層も重ね、これをチップ状に切断してから焼成して製造されます。しかし、チタン酸バリウムを主成分とする高誘電率系のコンデンサは、1300℃前後の高温焼成が必要で、内部電極に通常の金属を使うと、酸化したり溶融したりしてしまいます。このため、酸化しにくく融点が高い貴金属のパラジウムが、高価ながらやむなく使われていたのです。この問題を解決したのが、1980〜1990年代に TDKが業界に先駆けて開発したNi(ニッケル)内部電極積層セラミックチップコンデンサです。電子機器には多数の積層セラミックチップコンデンサが使われるため、安価な卑金属が使えれば、コストダウンにつながり貴重資源の節約にもなるからです。
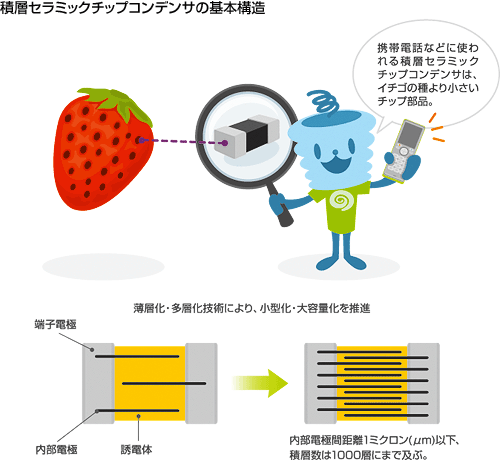
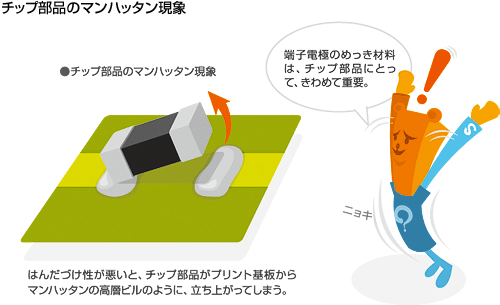
積層セラミックチップコンデンサなどのチップ部品の端子電極(外部電極)は、めっきによって形成されます。近年、電子機器から有害な鉛をなくすため、電子部品の基板への接合には、鉛フリーはんだが用いられるようになりました。しかし、はんだづけ性が悪いと、基板にマウントしたチップ部品がうまく接合せず、高層ビルのように立ち上がってしまうことがあります。これは“マンハッタン現象”と呼ばれます。そこで、接合性を向上させるため、端子電極のめっき材料や工法にも高度な技術が求められるようになりました。めっきは古くて新しい技術。めっき技術なくして、電子機器の小型化・高機能化も実現しません。
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです