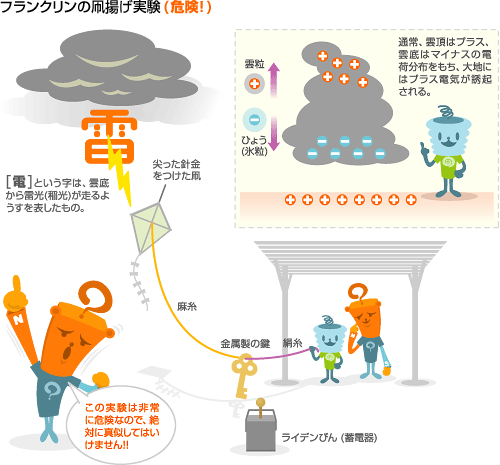電気と磁気の?館
No.10 半導体素子のルーツは天然鉱石の検波器

ラジオ、テレビ、携帯電話などに利用される電波は、可視光よりも波長の長い電磁波です。目には見えない電磁波をどのような装置で受信するかという暗中模索の研究の中から、無線通信やラジオ放送の技術が生まれ、ダイオードやトランジスタといった半導体素子も発明されました。無線通信の技術ルーツをたどってみると、難しそうな電磁波の世界もずいぶん親しみやすくなります。
携帯電話の電波でLEDが光る
ひところ携帯電話のアクセサリの1つとして、 “光るアンテナ”というのが流行ったことがあります。アンテナに取り付けたり、ぶら下げておくと、電話がかかってくるたびにLED(発光ダイオード)が光って知らせてくれるというもの。携帯電話の電波のエネルギーを利用して発光するので電池は不要です。
電話がかかってくると光るので、基地局から送られてくる電波を利用しているように思えます。しかし、基地局から届く電波は微弱なのでLEDを発光させるのは無理。実は電話がかかってくると、携帯電話は自らの位置を知らせるために電波を発信します。この携帯電話から発せられる電波のエネルギーによってLEDを発光させるのです。つまり発光のエネルギー源は自らの携帯電話のバッテリなのですが、電波のエネルギーが直接、光に変換されて目視できるというところがミソ。ちょっとしたアイデア商品でした。
光るアンテナの構成部品は、LEDとダイオード(高周波用のショットキー・バリア・ダイオードやゲルマニウム・ダイオード)、そしてコイル用の電線のみで、回路も実に簡単なものです。
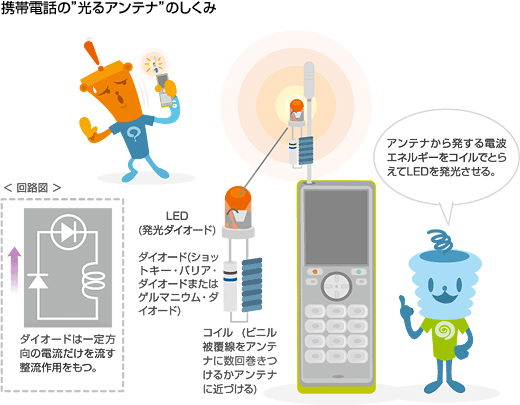
回路のポイントはダイオードにあります。ダイオードは順方向では電流が流れ、逆方向では電流が流れないという性質(整流作用)をもつ素子。LEDは直流電流で発光するので、コイルによってとらえた電波の高周波電流を直流に整流する必要があります。その役割をになうのがダイオードなのです。LEDも発光機能をもつダイオードの1種で、2本のリード線には極性があり、反対に取り付けると発光しません。
LEDもダイオードも比較的簡単に入手できるので、光るアンテナは手作りの理科実験・電子工作としても楽しめます。ただし、機種や電波の周波数・強さの違いなどにより光らないこともあります。また、携帯電話自らの電波エネルギーを利用するため、アンテナからの送信電波の強度は少し弱まります。
ヘルツが確認した火花放電の電磁波
身近な電子機器に多用されているダイオードは、p型半導体とn型半導体を組み合わせたpn接合のダイオードが主流ですが、そのルーツは点接触型ダイオードと呼ばれるもの。まだ電子の存在さえ知られなかった19世紀前半に、不思議な物理現象として発見されました。当時、ボルタ電池によってさまざまな物質に電流を流す実験がおこなわれた中で、ある種の鉱物や化合物に導線を接触させて電流を流すと、電流はある方向には流れて、逆方向では流れにくくなる性質があることが確認されたのです。この現象がやがて鉱石ラジオ(crystal radio)の検波器として利用されることになりますが、そのころはあまり注目を浴びませんでした。
その間、ヘルツの実験によって電磁波の実在は疑いないものとなり(1888年)、これを通信に利用しようというアイデアが生まれました。ヘルツの考案した実験装置は、ギャップを設けた電極に高圧を加えて火花放電を起こさせ、それにともなって発生する電磁波を、もう1つの電極の火花放電として検知するというもの。自動車やバイクのエンジンにおいて、点火プラグの火花放電がラジオにガリガリというノイズを生むのも、火花放電にともなう電磁波によるものです。
しかし、ヘルツの実験装置では遠距離の無線通信は実現できません。送信側の出力は火花放電の電圧を強めることでアップできますが、問題は受信側の装置にありました。電波(電磁波)の強度は距離とともに急激に減衰するため、微弱な電波でもキャッチできる感度のよい検波器が必要だったのです。そこで、フランスのブランリーはまったく新たなタイプの検波器を考案しました(1891年)。これは彼の名をとってブランリー管と呼ばれます。
ブランリー管はガラス管に金属粉(銀とニッケル)を詰め、両端に電極を設けた装置です。不思議なことに両端の電極に電池をつないでも電流は流れないのに、ガラス管が火花放電の電波を受けると電流が流れ出すのです。そこで、イギリスのロッジはこのブランリー管とベル(電鈴)を組み合わせ、電波を受信したとき電流が流れてベルを鳴らすという装置を発明しました。当時はまだブランリー管の検波作用を理論的に説明できませんでしたが、応用のほうがどんどん先行し、無線通信の時代が開幕することになったのです。
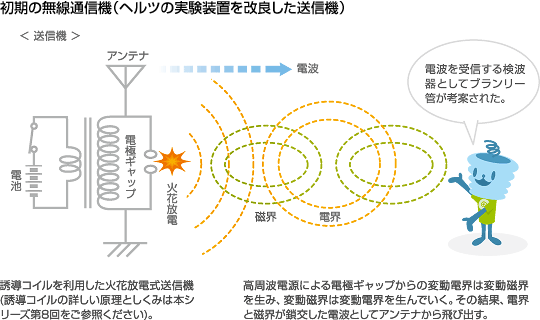
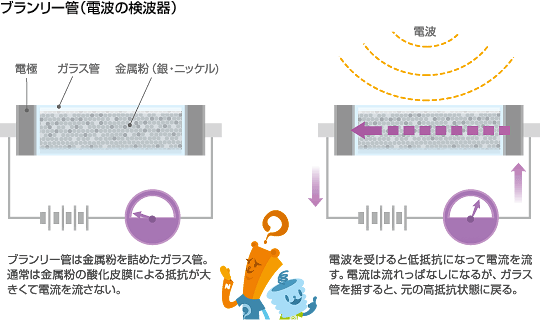
天然鉱石をダイオードとした鉱石ラジオ
ブランリー管の欠点は1回しか検波器として機能しないことです。というのも電波をキャッチしたあと、ガラス管の金属粉は密着して電流の通路ができ、電流は流れっぱなしとなってしまうからです。ブランリー管を用いた検波器はコヒーラ(cohere)と呼ばれました。コヒーラとは“密着して塊になる”という意味の英語です。密着状態から再び検波器として機能させるために、ガラス管を震動して金属粉をバラバラにする必要がありました。
このブランリー管の欠点を克服するため、ロッジの装置にたくみなメカニクスを導入したのはロシアのポポフです(1894年)。ブランリー管は電波を受けると電流を流すので、そのとき電磁石式のハンマーでガラス管を叩いて密着した金属粉の塊を崩し、たえず電波を受信できる状態を保つというしくみです。
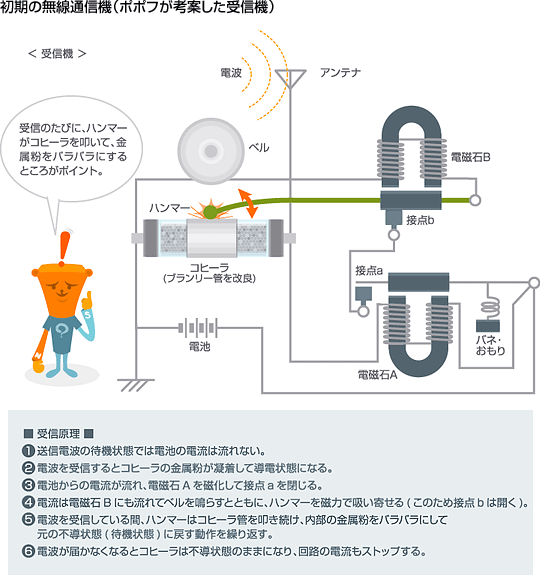
19世紀末から20世紀のはじめにかけては、ブランリー管の改良版といえるいろんなタイプのコヒーラが各国で考案されました。金属粉のかわりに水銀を用いたものもあります。イタリアのマルコーニも独自の工夫により大西洋横断無線通信の実験に成功しました(1901年)。初の真空管である二極真空管もまた、ブランリー管にかわる高感度の検波器として、フレミングの法則でおなじみのフレミングにより開発されたものです(1904年。二極真空管も英語ではダイオードと呼ばれます)。
こうした中でなかば忘れられかけていた天然鉱石の整流作用が日の目を見ることになります。方鉛鉱や黄鉄鉱などの結晶に、細い金属針を点接触させると検波器となることが確認されたからです。これを鉱石検波器といいます(アメリカのピッカードの鉱石検波器が有名ですが、欧米各国そして日本でも同時多発的に考案されたため、最初の発明者は特定できません)。鉱石検波器は機械的な駆動装置も電源も必要としないきわめてシンプルな検波器であるため、1920年代にラジオ放送が始まると家庭用ラジオに採用されて世界的に普及しました。これがいわゆる鉱石ラジオです。
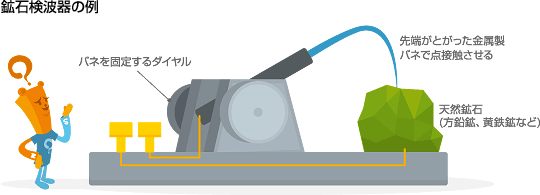
のちに鉱石検波器はゲルマニウム・ダイオードに代替されるようになりましたが、原理や構造はまったく同じものです。では、いったいブランリー管や鉱石検波器は、なぜ整流(無線やラジオでは検波という)作用をもつのでしょうか? この疑問を解く研究から半導体の理論と技術が発展し、トランジスタやIC、LSIなどの集積回路も開発され、今日のエレクトロニクス社会がもたらされたのです。前号でご紹介したように、真空管も照明用の電球技術から誕生しました。画期的な技術というのはゼロから出現するものではなく、過去の技術の継承・発展から生まれます。現代のハイテクもまた意外と古いルーツをもつのです。
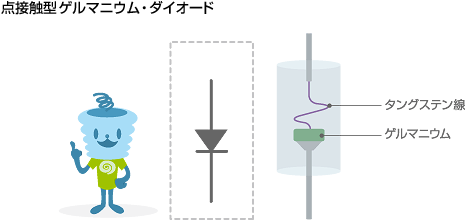
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです