電気と磁気の?館
No.9 照明はエレクトロニクスの原点

白熱灯や蛍光灯、水銀灯、ネオン灯など、都会の夜の照明は多種多彩です。照明はローテクのようでいて、なかなか奥深い技術。エレクトロニクスの誕生・発展にも大きく貢献しました。携帯電話のディスプレイや液晶テレビもバックライトなしには機能しません。その一方で、照明にはさらなる省エネ・省資源、環境配慮、長寿命化なども求められています。未来の照明はどう変わっていくのでしょうか?
照明とエレクトロニクスの関わり
照明とエレクトロニクスとの関わりは深く、発端は19世紀にまでさかのぼります。最初の電気照明はイギリスのハンフリー・デービーによるアーク灯の実験でした(1815年)。多くの観衆の前で演じられたこの実験には、何と2000個のボルタ電池が用いられました。電池に頼っては実用化は困難ですが、やがて蒸気機関を動力とする発電機が開発され、アーク灯は灯台を皮切りとして、工場照明や街灯などに用いられました。
アーク灯はギャップを設けた正負の電極に直流電圧を加えたとき生じる火花放電の光を利用するものです。しかし、アーク灯の電極は火花放電によって焼失してしだいに短くなっていくため、放電ギャップをたえず一定に保つ工夫が必要でした。このため時計のような歯車仕掛けにより、電極を押し上げていく工夫もほどこされました。しかし、これでは装置は複雑になり普及は望めません。
こうしたアーク灯の欠点を克服したのが、1876年、ロシアのパーヴェル・ヤブロチコフが考案した“電気ロウソク”です(白熱電球を用いた仏壇などの電気ロウソクとは異なります)。これもアーク灯の一種ですが、電源として直流ではなく交流を用いたところがポイント。平行な2本の電極に交流電流を流すと、先端部で火花放電が始まります。しかし、流す電流が交流であるため、2本の電極はともに同じ速度で焼失し、放電ギャップの調節が不要になります。電気ロウソクはこの2本の電極を4〜6組ほど立てたもので、1組の電極が焼失すると、次の電極に電流が流れるという仕掛けが取り入れられていました。
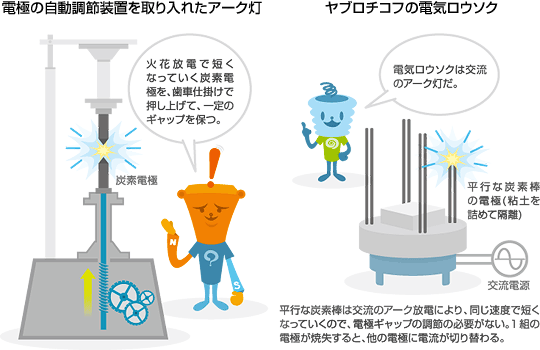
照明はエレクトロニクス誕生の原点
パーヴェル・ヤブロチコフの電気ロウソクは、約8〜12時間の連続照明を実現しましたが、やはり毎日、電極を取り替えるのは面倒であり不経済です。またアーク灯は室内照明には 眩しすぎるうえ、有害な紫外線を出すために、1820年頃から白熱電球の研究が始まりました。
白熱電球の発光の仕組みは、ガラス管の中のフィラメントと呼ばれる芯の部分に電流が流れると電気抵抗が生じて高温になり、光が発生するというものです。しかし、通常の金属は高温になると溶融してしまうのでフィラメントに使えません。そこで溶融温度が約3500℃の炭素が注目され、炭素線をフィラメントとする白熱電球がイギリスのジョゼフ・ウィルスン・スワンやアメリカのトーマス・アルバ・エジソンによって開発されました。

また、白熱電球の長寿命化にはフィラメントの酸化を抑えるために、ガラス管内の空気を抜いて真空にする必要がありました。ガラス管内の真空化については当時、物理学の先端分野であった真空放電の研究のために開発された真空ポンプが大きな役割を果たしました。それでもなお、当時の白熱電球は長く点灯していると、炭素フィラメントの蒸発によって断線してしまいました。1883年、エジソンは白熱電球の内部に金属棒を入れて、炭素フィラメントの蒸発のようすを調べていたところ、炭素フィラメントと金属棒は空間を隔てているのに電流が流れることに気づきました(エジソン効果)。
後に、エジソンの設立した会社に技術顧問として就任したジョン・アンブローズ・フレミングが、エジソンの研究を引き継ぐことになりました。フレミングは、無線受信機の動作を安定させるためにエジソン効果を応用することを思いつき、1904年に真空管を発明しました。真空管には電流の増幅や整流の機能があることから、無線機やラジオに使用されるようになりました。真空管はその後も多くの研究者の手によって進化を遂げ、テレビのブラウン管やレーダーなどの電子機器に欠かせないものとなりました。つまり、白熱電球を開発する意欲が、エレクトロニクスの誕生の原点となったのです。
真空管の役割は、のちに発明されるトランジスタ(半導体)に取って代わられ、その後、さらなるエレクトロニクスの発展につながることになります。
真空放電の研究の延長に蛍光灯が生まれた
放電管には電極に高電圧を加えて放電させる冷陰極放電管と、陰極となるフィラメントに電流を流して熱電子を発生させ、それを陽極へ流す熱陰極放電管があります。真空放電の研究の延長から生まれたのが蛍光灯です。
蛍光灯は内部に蛍光物質が塗布されたガラス管です。ガラス管の内部には水銀蒸気がとじ込められ、管の両端には放電電極(フィラメント)が取りつけられています。フィラメントに電流が流れ加熱されると、電極から熱電子が放出されて反対側の電極に向かって飛び出していきます。この時、放出された熱電子が内部の水銀蒸気に衝突することで水銀蒸気が紫外線を発生します。紫外線は人間の目には見えませんが、内部の蛍光物質と反応して人間の目に見える光(可視光線)に変わります。これが蛍光灯の発光原理です。蛍光物質の種類によって、「電球色」「温白色」「白色」「昼白色」「昼光色」といった様々な色の蛍光灯ができます。
液晶テレビのバックライトなどに使われる冷陰極管は、発光原理は蛍光灯と同じですが、フィラメントをもたず電極から電子を放出させています。
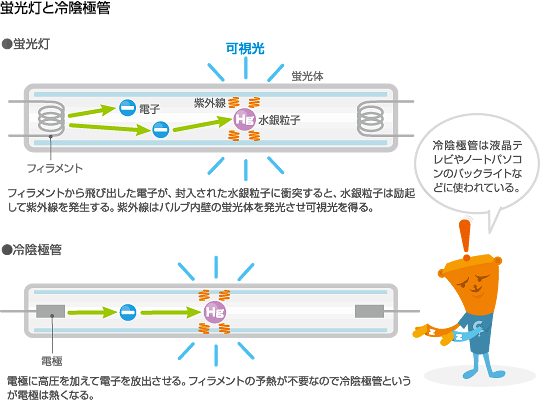
近年は無電極ランプと呼ばれる特殊な蛍光灯も開発されました。無電極ランプはその名のとおり電極をもたず、コイルによる高周波の電磁界変化によって水銀粒子を励起して紫外線を発生させるという方式です。電極がないためにきわめて長寿命なのが特長で、東京湾のレインボーブリッジなどの吊り橋をはじめ、ランプの取替え作業が困難な構造物の照明などに用いられています。
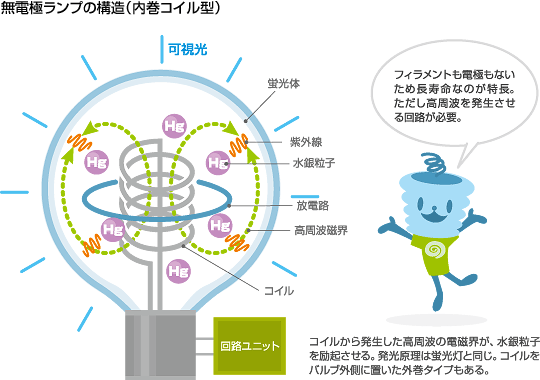
側面から照らす携帯電話のバックライト用LED
アーク灯、電気ロウソク、白熱電球、真空管、蛍光灯に続き、21世紀からはLED(発光ダイオード)が目覚ましい進歩を遂げて普及します。LEDの利点は消費電力が少なく寿命が長いという点です。
さて、携帯電話のカラーLCD(液晶ディスプレイ)のバックライトには、白色LEDが用いられています。太陽光はプリズムによって虹の七色に分解されることからわかるように、白色は単色光ではなく、さまざまな波長の光の集まりです。赤・緑・青(RGB=光の3原色)のLEDチップを並べても白色が得られますが、現在のところ白色LEDの主流となっているのは、青色LEDチップの光を黄色の蛍光体に透過させることによって白色を得るタイプ。青色と黄色の光を混ぜ合わせても、何とか白色に近い光が実現できるからです。いわば擬似的な白色光です。
ところで、バックライトとは呼ばれてはいても、携帯電話ではディスプレイの背面にLEDが置かれているわけではありません。薄型化を図るためにエッジライトと呼ばれる方式が採用され、ディスプレイの側面に3〜4個の白色LEDが搭載されています。光を側面から照射しているのに、ディスプレイ全体の明るさは均一です。これは反射シート、導光板、プリズムシートなどの特殊な多層構造により、光を均一に拡散する工夫がほどこされているからです。
また近年では、OLED(有機ELディスプレイ)の採用も進んでいます。OLEDは、有機EL素子に電圧をかけることで素子自体が発光します。OLEDはバックライトが必要ないため、携帯電話のさらなる軽量化、薄型化が実現します。
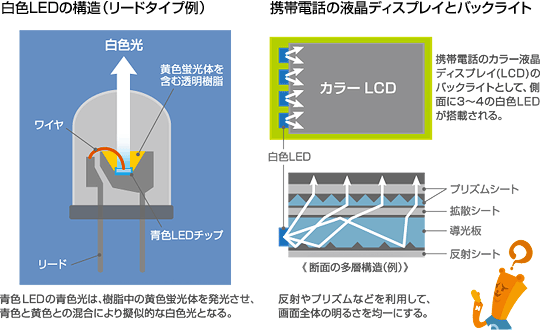
超大型のLED映像装置の輝きを支えるTDKの産業機器用電源
スタジアムなどの大型映像装置をはじめ、電飾看板やビルの装飾、駅や空港の表示機などに採用されているLEDディスプレイは、照明と映像技術を融合した装置です。LEDディスプレイは、多数の発光ダイオードを配列し、その発光によって映像を作り出す仕組み。そのLEDを表示する際には、電力を変換するためのAC-DCコンバータが必要となります。とくに、RGB(赤・緑・青)のLEDを組み合わせて、美しい映像を映し出すLEDディスプレイでは、RGBそれぞれの色を正確に表示するため、色ごとに最適な電圧に変換しなければなりません。こうした電力変換を行うのが、AC-DCコンバータで、TDKのグループ会社であるTDK-Lambdaブランドの電源製品は、高い変換効率と優れた信頼性を誇り、世界トップクラスのシェアを誇ります。
暗い夜を明るく照らすために生まれた照明は、時代ごとに進化を続けて、より明るく、より長く、より省電力にと発展を遂げてきました。照明から誕生したエレクトロニクスは、現在もなお、デジタルとネットワークによってさらなる発展を続けており、さまざまな社会問題を解決する希望の光となっています。
TDKは磁性技術で世界をリードする総合電子部品メーカーです







